
- リーダーインタビュー
- センパイの背中
科学・芸術・精神性を起点に、人と地球の生命の全体性を取り戻す:松島宏佑(ARu株式会社 CEO)
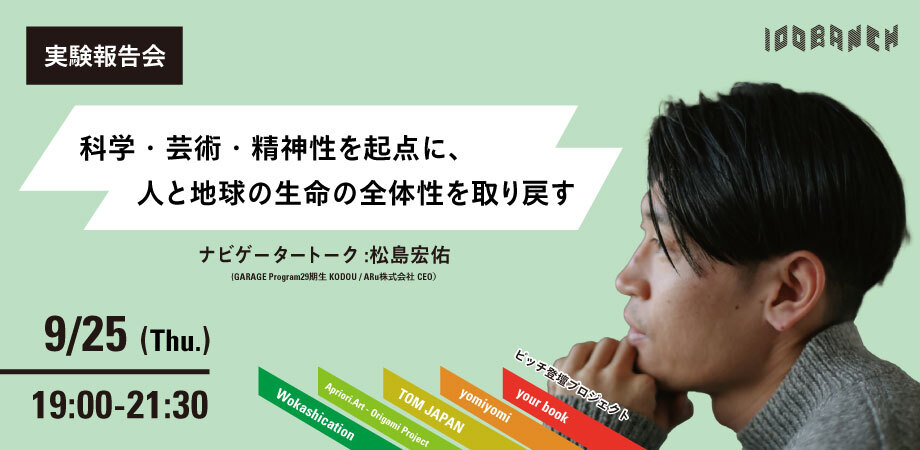
これからの100年をつくる若手リーダーのプロジェクトを推進するアクセラレーションプログラム「GARAGE Program」を終えたプロジェクトが、試行錯誤を重ねながら取り組んできた“未来に向けた実験”を広くシェアするイベントです。
また100BANCHでの挑戦を経て、プロジェクトを拡大・成長させた先輩プロジェクトによるナビゲータートークも実施いたします。
今回は、科学と芸術を組み合わせた体験創作やリーダーやクリエイターの創造行為への伴走支援を行うGARAGE Program29期生「KODOU」の松島宏佑さん(ARu株式会社 CEO)をナビゲーターとし、GARAGE Programを終了したプロジェクトが活動を報告します。
■概要
日程:9/25(木)
時間:19:00 – 21:30 (開場18:45)
会場:100BANCH 3F
参加費:無料(1ドリンク付き)
参加方法:Peatixでチケットをお申し込みの上、当日100BANCHへお越しください
■タイムテーブル
19:00〜19:05:OPENING
19:05〜19:15:100BANCH紹介
19:15〜19:45:ナビゲーター活動紹介トーク
19:45〜20:00:質疑応答
20:00〜20:50:プロジェクト 活動報告ピッチ
・your book
・yomiyomi
・TOM JAPAN
・Apriori.Art – Origami Project
・Wokashication
・utsuRe
・COCOREACH
20:50〜20:55:今後のイベント紹介
20:55〜21:30:ネットワーキング
■こんな方にオススメ
・100BANCHに興味がある
・GARAGE Programに応募したい
・直接プロジェクトメンバーと話してみたい
・アートとテクノロジーの融合に興味がある
・リーダーやクリエイターへの伴走支援に興味がある
■ナビゲーター情報
松島宏佑さん|ARu株式会社 CEO
宮城県生まれ。宇宙の誕生に興味を持ち、大学で素粒子物理学を学ぶ。2011年3月11日に東日本大震災が発生し地元が被災したことをきっかけに、社会起業家としてNPOを創業。その後、コンサルティングファーム、共創型戦略デザインファーム、ソーシャルデザインファーム等を経て、2018年より、詩人、アーティストとして活動を開始。新しい詩の表現を試みた「触れる詩」「地球、この孤独な生命展」、時間がテーマの「コドウ時計」などの作品を経て、生命を光で表現する < kodou > の営みを開始。2021年1月、活動を世界に届けるため、kodou inc を設立。共通するテーマは、生命への畏怖。鑑賞者が作品の一部となる作品を手がける。
ー
松島は2019年12月に100BANCHに入居。ヒトの鼓動のリズムを光に変換し、10人から数万人という単位の光を1つの場に集め、その場だけの表現作品を作るアートプロジェクトを行いました。現在は、科学と芸術を組み合わせ、<Earth-sensing> をコンセプトに、世界の見え方が変わってしまう体験創作を行いつつ、思想あるリーダーやクリエイターの創造行為への伴走支援も行っている。
ー
■登壇プロジェクト紹介
・your book:坂田陽菜 #障害 #自分らしさ
さみしさを一人で抱えなくてもいい、「その子だけの本」で、きょうだい児も主役になれる社会へ
きょうだい児(障がいや難病を抱えているきょうだいがいる人)と親の気持ちをつなげることを目指すプロジェクト。障がいを持つ本人とはまた違う、きょうだい児特有の悩みを親に伝えるきっかけをつくります!
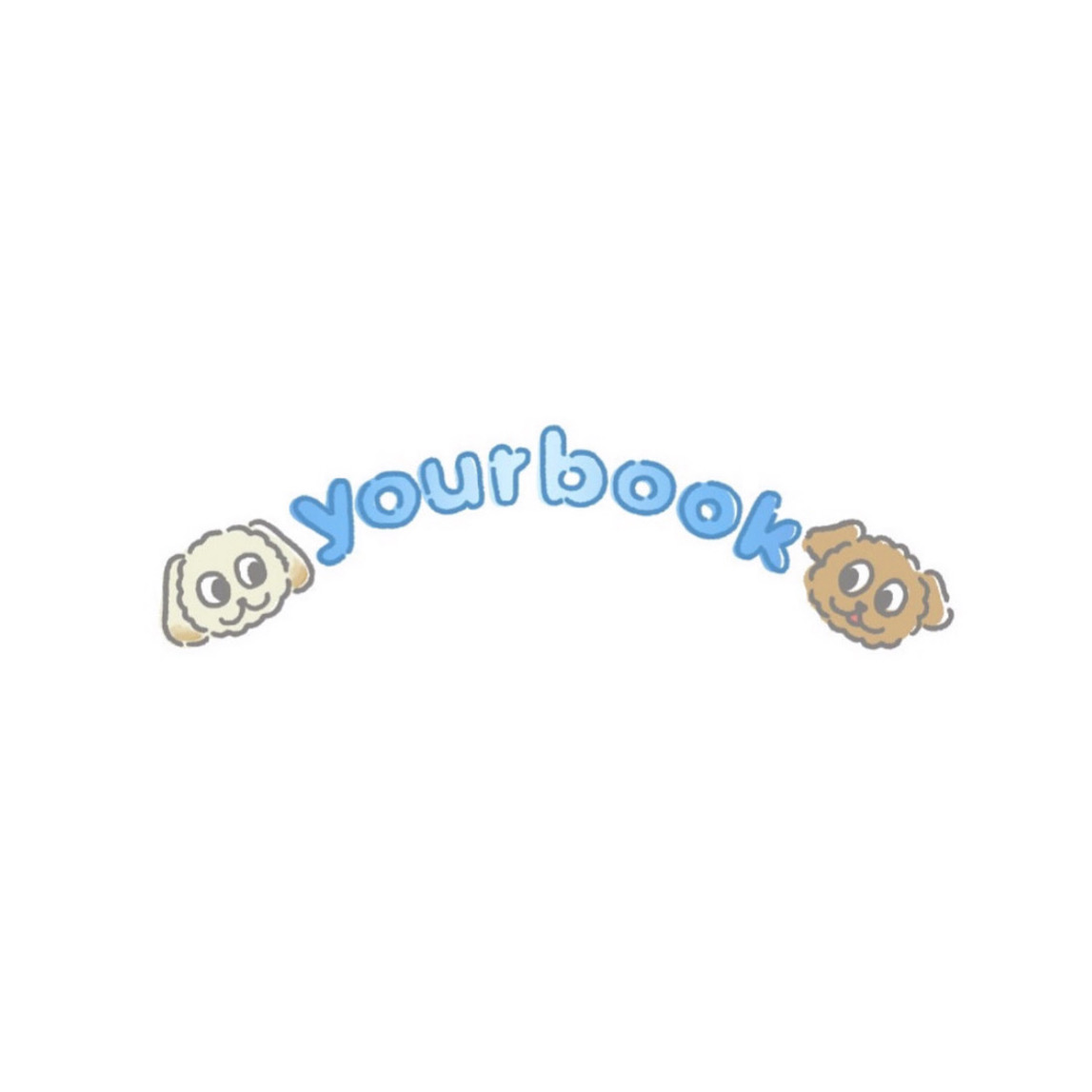
・yomiyomi:仲村怜夏 #死生観 #哲学
記憶の主権を人からモノへ。思い出が日常空間に編み込まれる社会を実装する。
「記憶がモノを通して生き続ける世界」を目指すプロジェクト。スマートフォンをかざすだけで、1秒で思い出がよみがえる、ICチップ内蔵のデジタルステッカーで「モノに記憶を宿す」という新たな記憶の在り方を社会に提案していきます!

・TOM JAPAN:北島未菜 #ものづくり #ケア
障害のある当事者(Need-Knower)の「1の困りごと」から、誰もが快適に過ごせる社会を共創
支援機器を共創し、誰もが快適に過ごせる世界の実現を目指すプロジェクト。多分野の学生・専門家がチームを組み、テクノロジーと当事者の声を掛け合わせることで「今ここに必要な」支援機器を社会に届けます!

・Apriori.Art – Origami Project:Hiro Kano(加納宏徳) #折り紙 #アート
世界最大の折り紙の祭典「Origami World Expo」を開催! 日本発の「折り紙産業」を創造する
多くの人が楽しめるORIGAMIカルチャーと折り紙産業の創造に挑戦するプロジェクト。画家や音楽家などと同じように、折り紙アーティストが稼げる職業になっている世界を目指し、試行錯誤を続けます!

・Wokashication:清水透和 #和菓子 #デザイン
和菓子に関わるきっかけをデザインし、和菓子文化が息づく未来を探究する
デザインの力を活用し、和菓子に触れる機会を創出することで、和菓子文化の継承と革新を目指すプロジェクト。現代・未来のライフスタイルに合わせた和菓子の在り方をデザインの視点から提案し、和菓子文化が息づく可能性を探求します!

・utuRe:稲垣凛 #カメラ #旅
「「誰のものでもないカメラ」が辿る旅路で、人と人との信頼を描きたい!」
カメラを媒介に人と人のつながりを誘発し、「信頼」の移り変わりを探ることを目指すプロジェクト。カメラを主人公とし、新しいカメラのあり方をデザインする挑戦に注目です!

・COCOREACH:島田早織 #心 #センシング
「あなたのココロにリーチ!感情の可視化から、新たな社会基盤を創造する」
感情の共有・定量化を通して生体情報を新たなインフラとすることを目指すプロジェクト。腕輪型デバイスの開発や感情分析システムの実装などスピード感を持って活動を進めてきた成果に注目です!

■GARAGE Programへの応募検討者対象のガイダンスも同時開催!

GARAGE Program応募検討者の皆様へ向けたガイダンスも実験報告会当日に実施します。100BANCHの概要説明や応募にあたっての質疑応答、施設見学などを予定しております。
プロジェクトの内容を整理するのに有効なワークシートや100BANCHの活動を記録したBANCH BOOKなどのプレゼントもご用意!応募を検討されている方もぜひ実験報告会にご参加ください!
🔽参加申し込みはこちら

your book リーダー坂田陽菜
2007年生まれ。玉川学園高等部12年生。9年生の自由研究から「障がい者差別」に興味を持ち、調べている。昔から国語が得意だったため、「言葉」を使った方法で親ときょうだい児をつなげたいと考え、「本」というアイデアを思いついた。プロジェクト名は、大好きな姉の行っている活動「my doll」と掛けて「your book」と名付けた。

yomiyomi リーダー仲村怜夏
2000年生まれのデザイナー兼お花屋さん。九州大学休学中。2023年、株式会社ゆめみにてプロダクトデザイナーとしてキャリアをスタートし、グッドデザイン賞を受賞。フラワーアーティストとして自身のブランドも手がける。衝動ドリブンで、漫画と音楽、そして妄想を形にするのが大好き。

TOM JAPAN リーダー北島未菜
福岡県福岡市出身。作業療法士。京都大学修士卒。当事者のニーズ起点でプロダクト開発を共創する場をつくりたいと思い、TOM JAPANを創設。多分野・当事者と支援機器を共創し、共生社会の実現を目指す。好きな言葉は「みんなちがってみんないい」。

Apriori.Art Co-founderHiro Kano(加納宏徳)
本プロジェクトの共同創業者。小学校をドロップアウトし中高大は行かず、10年間独学を続け英語、フランス語、ウェブ構築を身に着ける。その後、翻訳業やEC運営、起業やスタートアップ、代理店勤務などを経験した後、現在は外資IT企業にて、ウェブマーケティングマネジャーを務めるなど、ユニークな経歴の持ち主。
Apriori.Artの構想は2019年ごろから温めており、やっと実現できる機会が掴めたことにとてもワクワクしている。鳥や羽のある生き物の折り紙作品が好き。

Wokashication リーダー清水透和
2001年生まれ群馬出身。 大学・大学院でデザインを専攻。体験デザイン・立体デザインを主軸としている。自分も仲間もユーザーもが、自然と面白がれる提案を行うことをモットーにデザイン活動に取り組んでいる。

utsuRe リーダー稲垣凜
愛知県名古屋市出身。立教大学現代心理学部映像身体学科在学中。サンタにDSを頼んだのにカメラがやってきてから大好きな長年の趣味である一方、ときに囚われている。高校1年生の時に-40度のカナダの極寒地で一から関係性をつくったことをきっかけに、「結局は人間同士」という価値観を持つ。大学ではErasmus University Rotterdam に留学し、映像とメディアコミュニケーションの観点からカメラを通した信頼関係の構築を考えている。オレンジジュースで元気になる。

100BANCH