人と人の間にある「アイス」を溶かし、仲良くなれる世界を探究する研究所

be♭
人と人の間にある「アイス」を溶かし、仲良くなれる世界を探究する研究所
-
be♭リーダー/ 研究員 伊藤詩奈


全ての人がコミュニケーション可能な未来をつくる









100BANCHに入居する「障がい」をテーマにする4つのプロジェクトの代表が手を組んだ組織体です。
日本語が理解できない「言語難民」に対し教育を提供する『NIHONGO』の永野将司、知的障がいのあるアーティストの作品をモノ・コト・バショに浸透させる『MUKU』の松田崇弥、点字と墨字という異なった世界をつなげるデザインを行う『Braille Neue』の高橋鴻介、手話をコミュニケーションツールとしたゲームを提供する『異言語Lab.』の菊永ふみの4名が、各自の専門領域を繋げることで、それぞれのコミュニティの垣根を超えて新しい伝達方法を創造します。
100BANCHに入居する「コミュニケーション」をテーマにした4つのプロジェクトが、全ての人がつながる未来をつくる
「どんな人でも理解可能なコミュニケーション」である「未来言語」は創造できる。
我々は「視覚障害/聴覚障害/知的障害/外国人といった、いわゆるマイノリティと言われる人々のコミュニケーションの中に未来言語の種が眠っている」という仮説を立てた。これはエクストリームの中にこそ、メインストリームを変革するヒントが眠っているとするインクルーシブデザインの文脈に則ったものである。
そのエッセンスを抽出するために、これから3ヶ月、月1回のペースで未来言語を探るワークショップを開催していく。
これまでのワークショップの検証結果を確認したうえで、「未来言語×◯◯」といった未来言語の応用的なワークショップを実施していく。
現在、メインストリームのコミュニケーションとして使われている音声や文字は、障害や文化などによって大きな壁が生じている。これらの壁を超えて全人類が同じ言語を使えば世界は平和になるのではないか?
我々は音声や文字などの既存の言語を超えてコミュニケーションが可能な「未来言語」を創造する。

共同代表永野 将司
株式会社NIHONGO代表取締役 大学在学中の2007年から日本語を教え始める。これまでに国内外の大学・日本語学校などで1,000人以上の外国人に日本語を教えてきた。Tokyo Startup Gateway ファイナリスト。

共同代表菊永ふみ
ろう者。福祉型障害児入所施設で聴覚障害児の生活支援に携わる。企業の社会貢献活動の一環として社員と聴覚障害児との交流企画を担当、2015年、異言語脱出ゲームを発案。

共同代表松田崇弥
株式会社ヘラルボニー代表取締役 小山薫堂率いる企画会社オレンジ・アンド・パートナーズ、プランナを経て独立。福祉施設に所属するアーティストの作品をプロダクト化するMUKU代表。

共同代表高橋 鴻介
1993年12月9日、東京生まれ秋葉原育ち。慶應義塾大学 環境情報学部卒。卒業後は広告代理店で、インタラクティブコンテンツの制作や公共施設のサイン計画などを手掛けつつ、発明家としても活動中。墨字と点字を重ね合わせた書体「Braille Neue」、触手話をベースにしたユニバーサルなコミュニケーションゲーム「LINKAGE」など、発明を通じた新規領域開拓がライフワーク。

営業担当大田 雄之介
東北学院大学 経営学科卒。現在は株式会社ヘラルボニー 海外統括・オペレーションディレクターを担当

広報担当岡崎良士
難聴者。10年間、出版・編プロに勤務し、雑誌を中心とした企画・編集・取材・原稿執筆のほか、広告関連のディレクター職を兼務。転職後、福祉型障害児入所施設(主に聴覚障害)の児童指導員として約5年働く。現在は、一般企業に勤務。

ニギヤカシ大久保勝仁
国連子どもと若者メジャーグループ都市開発アジア統括。持続可能な社会のための国際的な枠組みに向け、政策提言と交渉を行う。ウンベルト・エーコ著『完全言語の探求』と大学3年生の時に出会い、普遍言語を作り出すことに関わりたいと願う。未来言語では、”言語”を超えて誰かをニギヤカすことができるのかという問いに挑む(予定)。白Tが大好き。

ライター関口智子
営業、営業事務、クリエイティブディレクターを経た後、身近な人が表現する場、他者に伝える手助けをする為に、編集/ライティングでフリーランスへ。働き方の実験中。個人でも絵とJazzを中心にマイペースな創作活動も行なっている。

共同創案者河カタ ソウ
コピーライターとしてキャリアをスタート後、クリエイティブディレクター / プロジェクトマネージャーとしてWebサイト、広告、イベント等、様々なプロジェクトに従事。その後独立、現在は言葉の視点から主にブランディングやディレクションを行う。猫好き。

東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院 准教授、環境・社会理工学院 社会・人間科学コース 准教授伊藤亜紗
2010年に東京大学大学院人文社会系研究科基礎文化研究美学芸術学専門分野を単位取得のうえ、退学。同年、同大学にて博士号を取得(文学)。学術振興会特別研究員をへて、2013年に東京工業大学リベラルアーツセンター准教授に着任。2016年4月より現職。著書に『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社、2015年)、『目の見えないアスリートの身体論』(潮出版、2016年)、『どもる体』(医学書院、2018年)など。WIRED Audi INNOVATION AWARD 2017受賞。

株式会社リ・パブリック共同代表市川 文子
広島県出身。慶應義塾大学大学院にて修士課程修了後、当時まだ珍しかった人間中心デザインの職を求め、フィンランドに渡航、携帯事業メーカー・ノキアに入社。世界各国でのフィールドワークから課題を起点とした製品やサービスの開発に従事。退職後、博報堂イノベーションラボ研究員を経て、2013年株式会社リ・パブリックを創設。現在は持続可能なイノベーションをテーマに地域や組織における環境整備およびプロセス設計の研究・実践を手がける。広島県事業「イノベーターズ100」ディレクター、グローバル・リサーチ・ネットワーク「REACH」日本代表。監訳に「シリアルイノベーター~非シリコンバレー型イノベーションの流儀」。
プロジェクトの歩み
入居開始

障がい・言葉の壁を乗り越え、次世代のコミュニケーションを見つけるワークショップ「未来の言語」を開催 8月18日(土)15:00~ 渋谷・100BANCH

未来言語シンポジウム

U35の次世代が描く未来とはー?100BANCH Garage Program、10月は6プロジェクトが入居。12月入居の応募〆切は10/22(月)23:59

未来言語×よしもと 『次長課長 河本&麒麟 田村たちとつくる、笑いの未来言語』

トライ・アンド・エラーの結晶がここに 〜GARAGE Program実験報告会〜

言葉や文化を超えていく“お笑い”のかたち――「次長課長 河本&麒麟 田村たちとつくる、笑いの未来言語」イベントレポート

未来のスポーツ -Diversity & Inclusion 第2弾- 障がいの壁も、言語の壁も乗り越えて、すべての人が分かち合えるスポーツは実現できる?
@パナソニックセンター東京

ナナナナ祭2019が開幕 メンターアワードも決定 第1弾は「うどんセレモニー」「地球の味レストラン」ほか

逆境が未来へのステップに(VOL.1) コミュニケーションを欲する気持ちが隔たりを壊す Braille Neue / 未来言語:高橋鴻介
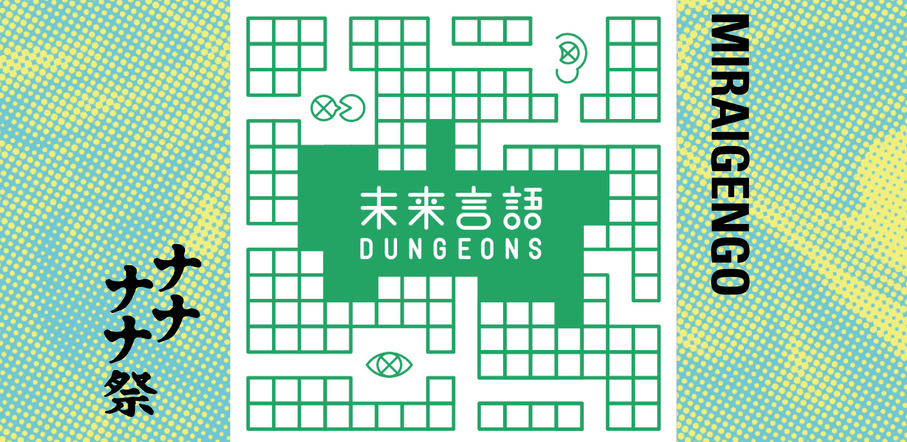
未来言語ダンジョン /ナナナナ祭2020
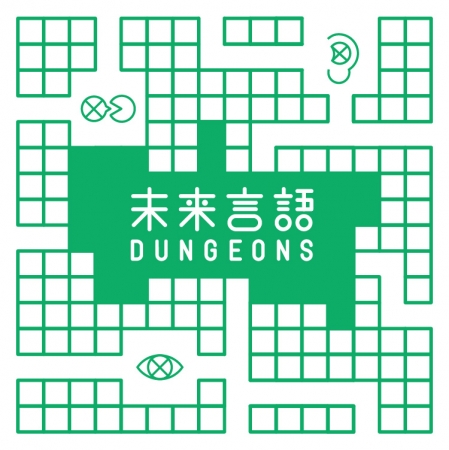
「みえない」「きこえない」「はなせない」状態でのコミュニケーションにチャレンジする未来言語がオンライン企画『未来言語ダンジョン』を開催(7/31、8/1、8/2)【ナナナナ祭2020】
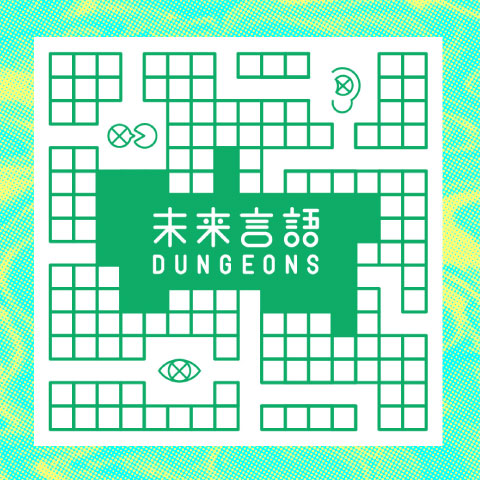
コミュニケーションの第六感? 相手を思う感覚「思覚」を育む未来言語ダンジョン

GARAGE Program メンバーが語る—— “今だからこそ”、未来に向けて大切なキーワード(Vol.2)
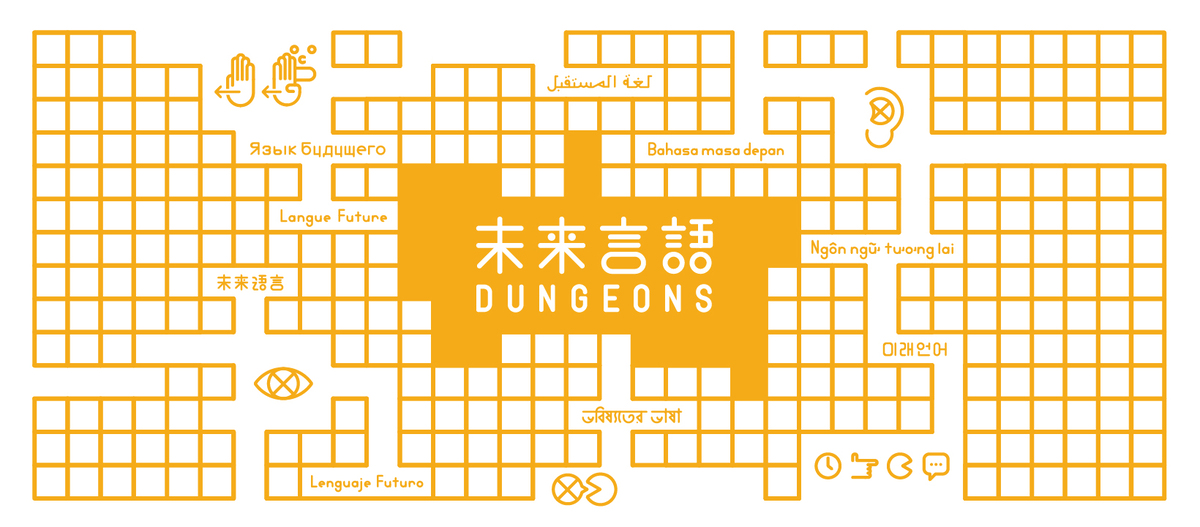
「みない」「きかない」「はなさない」状態で、新たなコミュニケーションは生まれるのか?!オンラインイベント『未来言語ダンジョン』3月に078KOBEにて開催!

未来のコミュニケーションを探る「未来言語」が、「見ない」「聞かない」「話さない」で遊ぶボードゲーム『テレパシ』の予約販売を本日スタート

100BANCHから、オランダへ。 デザイナーの海外挑戦のリアルを語る報告会を開催
コンタクト