人と人の間にある「アイス」を溶かし、仲良くなれる世界を探究する研究所

be♭
人と人の間にある「アイス」を溶かし、仲良くなれる世界を探究する研究所
-
be♭リーダー/ 研究員 伊藤詩奈

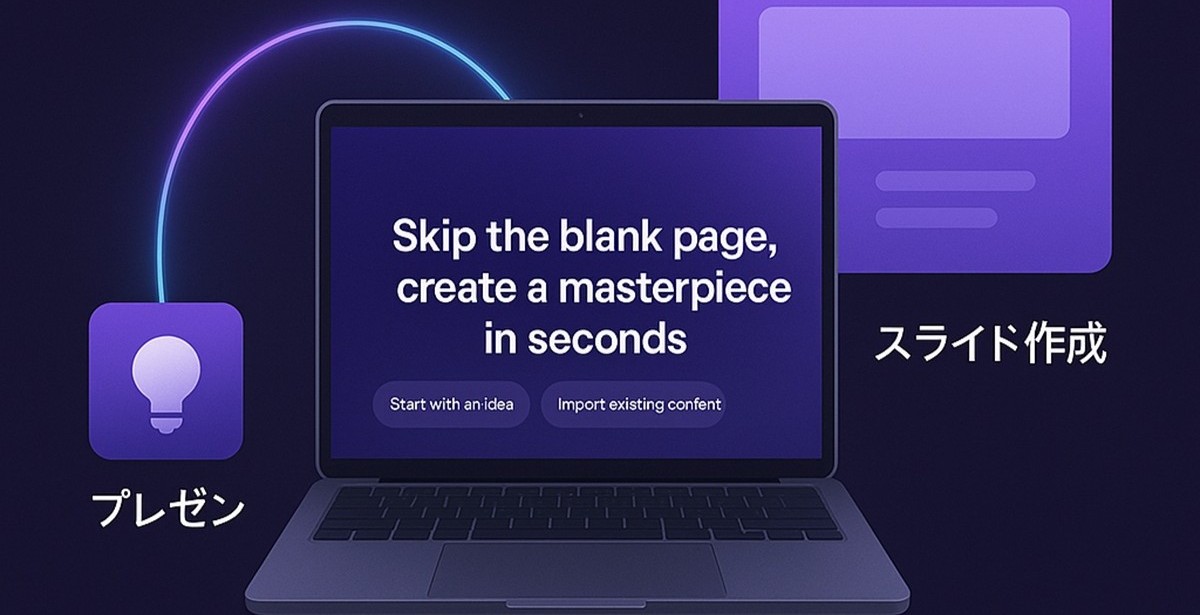
「偶然の出会いを生み出す」AIが、新しい挑戦にあふれた社会を実現する

私たちは「偶然の出会い」を生かして、新しい挑戦があふれる社会を目指すプロジェクトです。
情報化とAIが発達を遂げる現代社会において、人間がより主体的に挑戦し、活躍する未来を加速させていきます。「セレンディピティ」と呼ばれる「偶然の出会い」に着目し、それをきっかけとした新たな挑戦を後押しするAIやサービスの開発に取り組んでいます。どれほど「高度な」AIが登場したとしても、これまでにないような新しいモノやコトに触れ、挑み続けることこそが人間らしさであるはずです。私たちはそうした「馬鹿らしく人間らしい面白さ」に満ちた社会の実現を目指しています。
普段、AIやソフトウェアの開発を主な仕事とする中で、AIの普及や情報化社会の進展が、人々の中に「失敗への恐怖」や「新しいことへの挑戦・変化への忌避」をむしろ助長しているのではないかと強く感じるようになりました。
AIや過去の経験から学ぶことで、確かに失敗を減らし、より最適な選択を導くことはできます。
しかし、人類の発展とは、数えきれないほどの失敗や、非最適な選択の積み重ねによって築かれてきたものではないでしょうか。
だからこそ、私は「最適化されないこと」の中にある人間らしさや創造性を引き出し、それを支えられるようなAIやサービスをつくっていきたいと考えています。
ITによる情報化、さらにはLLMをはじめとするAIの発展によって、人類の生活や社会全体はこれまでになく最適化が進んできました。
たとえば、人材サービスではAIが求職者に最適な職業を提示し、マッチングアプリではその人に最も合う相手を紹介するようになっています。
しかし、そうした便利さの裏で、人の人生における「豊かさ」は本当に失われていないのでしょうか。
最適化によって出会わなくなった「失敗」や「偶然の経験」から生まれる面白さや、思いもよらない影響を、私たちは見過ごしてはいないでしょうか。
常に「これまで上手くいった」選択ばかりを選んでいては、きっと出会えないものがあるはずです。
人間関係、ビジネス、教育、エンタメ――あらゆる分野でAIが活躍する今こそ、あえて「最適でない選択」や「偶然の出会い」が、社会に新たな価値をもたらすのではないでしょうか。
AI社会の中で、人々が新しいものやことに触れ、挑戦できるよう支援するプロダクトを探し、つくり出していきたいと考えています。
その第一歩として、3カ月間では「自分の好きなものを簡単にプレゼンできるサービス」――AIによってPowerPointのスライドを手軽に作成できるアプリケーションの開発やリリース、ユーザーテスト等に取り組んでいきます。
スライドを簡単に作成できるようになることで、誰もが自分の好きなものやことを、すぐに・手軽に共有できるようになります。それによって、人々が新しいものや考え方に触れる機会を増やし、世界を少しずつ広げていけるのではないかと考えています。
より多くの人に新しい出会いを提供する
1. アプリのスモールリリース
2. ユーザーテストとしての5分で簡単にプレゼン準備ができる趣味共有会の開催
3. 新規アイデアの企画
AGI(汎用人工知能、Artificial General Intelligence)と呼ばれるAIが誕生した社会の中でも、これまでにないような新しいものやことに触れ続け、チャレンジし続ける、ある意味「馬鹿らしく人間らしい面白さのある社会」の実現。

Next Serendipity リーダー髙松周平
1998年神奈川県生まれ、東京大学 新領域創成科学研究科卒。在学中はNHK学生ロボコンに打ち込みエンジニアの道へ。研究でのプラズマ、仕事でのロボット、AI、web、ゲーム、教育等、幅広いエンジニアリングに取り組んできた。現在はフリーランスとしてさまざまな事業に取り組んでいる。