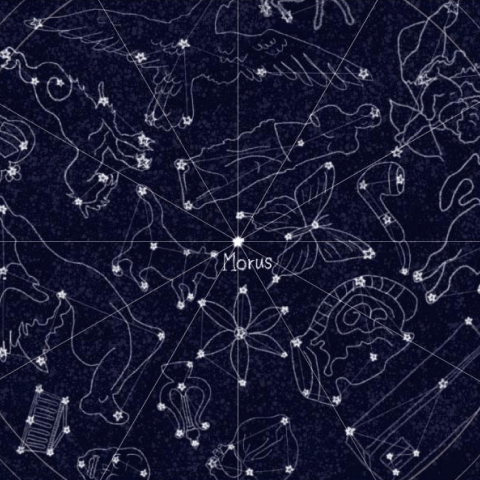
MUJO
渋谷で死と出会う
-
代表 前田陽汰


高齢化社会を迎えた日本。家族葬や自動搬送式の納骨堂など、新しい弔いのあり方が一般化するとともに、想い出を共有するために故人のSNSを残す「追悼アカウント」や死後も故人と話せる「生成AI」が誕生するなど、技術の発達により、生と死の境界も曖昧になっています。
コロナ禍以降、100BANCHのプロジェクトでも「死」に関連するものが増えています。100BANCHでは、2023年2月に弔いの風習や足跡が残る岩手県遠野市でリサーチを行いました。ナナナナ祭2023の2日目である7月8日にはその報告も兼ねて、トークイベント「弔いの未来 −その意味・儀式・生者との境界−」を開催しました。
登壇メンバーは、遠野のリサーチガイドも務めていただいた民俗学者・学習院大学教授の赤坂憲雄さんと、死をテーマに活動する100BANCHのプロジェクトメンバー。遠野のリサーチの報告、登壇者同士でのクロストーク、会場からの質問を交えたダイアローグの様子をレポートします。

|
登壇者 赤坂憲雄|民俗学者/学習院大学教授/福島県立博物館元館長 前田陽汰 |MUJOプロジェクトリーダー /株式会社むじょう代表/GARAGE Program50期生 |
イベントは2月に行われた遠野のリサーチの報告からはじまります。死にまつわるプロジェクトを行うメンバーは、遠野の地を訪れ何を感じたのでしょうか。
100BANCH澤田が遠野でのリサーチ概要を伝えながら、登壇者に話を聞いていきます。

澤田:遠野物語の舞台である岩手県遠野市をリサーチするにあたり最初に向かったのが、まだ雪が残る山奥にある「五百羅漢」。ここは200年あまり前に東北地方を襲った大飢饉の死者を供養するため、大慈寺の義山和尚が五百体の羅漢像を彫った供養の場です。しっとりと苔むした花崗岩の表面を見ると、羅漢像が刻まれています。

山本:五百羅漢の場に立ったときに、小さい小川の水の音や木のこすれる音や空気や湿度とか、経年劣化している石から感じられる時間とか、目に見えない色んなものを感じたんですよ。魂なのかな、弔われた何かを共有している感覚になっていました。
澤田:次に向かったのが遠野市内の善明寺です。ここには江戸から大正にかけて死者を供養するために友人や遺族が奉納した「供養絵額」が残ります。岩手県の中部特有の風習である供養絵額は死者の心残りや好きなものを遺族たちから聞き取りをして、人気絵師に書いてもらったものです。
鴻戸:友達同士で集まり、『あの人はこれが好きだったから描いてあげよう』というように、楽しく話していたんだろうなと想像しました。
澤田:最後に向かったのは『遠野物語』でも語られる姥捨て山「デンデラ野」。かつては60歳を超えると集落からデンデラ野に送られていました。赤坂さんから「共同で小さな小屋を建てて暮らしていたけれど、東北の山奥の厳しい気候では冬を越せなかったのだろう」と話を聞いて切ない気持ちになりました。デンデラ野からは、もともと暮らしていた集落がそばに見えます。

赤坂:はじめて来たときに印象的だったのは、集落の家の裏手の小高い丘の上にデンデラ野があり、反対側に「ダンノハナ」という山の中腹の共同墓地が見えること。生きている人の世界から、老と死の世界が見えて、いつでも意識されている。人の一生が組み込まれた空間デザインだと思うんです。僕らが生きる現代では、死の世界を意識する空間というのは基本的にはありません。それゆえに自分が死んでいくことを実感できなくなっている。その違いが死生観に与える影響は大きいと思います。
鴻戸:「供養絵額」を見たときに、すごく明るくて、故人が今の世の地続きの世界でまるで生きてようだなと思ったんです。私のおばあちゃんも亡くなっていますが、もう二度と会えないという意味では、海外に引っ越した友達と、距離感は一緒かもしれない。そう思ったときに、死の世界はパラレルワールドとして捉えらえると思ったんです。同じように供養絵額も故人がこことは違う世界で生きていると思って、描いてもらっていたとも考えられますよね。

前田:僕は遠野には行けなかったのですが、五百羅漢が苔むして経年劣化をしている話を聞いて、自分のプロジェクトに通じるものがあると思いました。僕は、会社の事業として、亡くなった人をインターネット上で弔い、故人の写真を共有できる「追悼サイト」をつくったんです。その際、Webでは故人の写真をすべて残せてしまうから、これから生きる人の足かせになると思ったんですよね。そこで、Webは3日で消えて、黄ばみや時間経過が感じられるアルバムで写真を残せるようにしました。
赤坂:供養絵額は明るいですよね。東北は死の記憶を大切にしている。だから、死が持つマイナスの恐れや穢れと戦って、時間をかけて苔むすまで浄化していく仕掛けを作っているんだと思います。でも一方で、東北には怖いものもいっぱいあります。例えば、婚礼の絵や花嫁人形を奉納する習俗があり、家族で病気や嫌なことが続いたときにイタコの所に行くと20年前に死んだ子の祟りだと言われたりする。その子の魂を鎮めるために、冥界で結婚できるよう、花嫁の人形を奉納するんです。怖いですよね。君たちには怖いところは見えてない。それでいいけれども、怖いものもたくさんあるんです。

山本:怖さと言えば、僕は葬儀場で働いているのですが、作られた死の場所なので怖さは感じないんですよね。五百羅漢もそうでした。一方で、富士の樹海のような場所はとても怖さを感じます。実際に足を運んだことがあるのですが、公道から外れた所を歩いていたら、酒や薬が転がっている。人が最後の時を過ごした跡が残っていたんです。さらに、周りを見ていたら、遠くにピクリとも動かない人が立っている。よくよく見ると首つりをした遺体が枝にぶら下がっていたんですね。そんな生々しい死の光景から100mぐらいの距離の道路では、幼稚園児がハイキングしていたりします。その後、僕の祖母が亡くなって、葬儀があったときに、僕たちの日常には見えない死があると思いました。毎日どこかで人が死んで弔われている。今も近くのビルで首をつっている人がいるかもしれないし、死とは普遍的で日常的なことなのだと感じました。僕はずっと死に関心がありますが、唯一想像できる絶対に訪れる未来だからこそ考えざるを得ないんです。

少子高齢化社会の日本では、ますます死が日常的なものになり、弔いの在り方も変化していくことが予想されます。そんな社会を目前に、私たちが「弔い」について考える意味とは?
前田:僕は地域創生で有名な島根県海士町の高校に進学したんですけど、そのときに「成長すること一辺倒でいいんだろうか?」って疑問を感じたんです。20年後には明らかに人がいなくなる状況の中で、むしろ「どう終わるか」を考えることが大事だと思ったんですよね。現実はそっちに向かっているのに、誰もが「衰退」から目を背けて語ろうとしない。それは、成長物語に逃げているのだと思います。「死」という「終わり」に対峙することで、地域の「衰退」にも目を向けることができるようになると思うんですよね。なので、終わりや死をリデザインするという取り組みを行っています。
赤坂:思い出したのは、震災後に行った「国東半島芸術祭」の「いりくちでくち」という演劇作品です。古い家を解体した木が、浜の捨て場に集められている。分別をしながら、最後は木くずになって、カブトムシの住処になる。この作品は生命の循環を表しているんですね。森の木が切られて家になり、200年間かけて人と暮らしを共にしながら朽ちて、その場所にたどり着いて、命の苗床になる。その作品の浜の捨て場は、東日本大震災の後に見た津波で流された瓦礫の集積所と似ていて、びっくりしました。作品は、静謐で穏やかな気分になるけれど、瓦礫の集積場は人形や服が瓦礫の中に分別されずに混ざっていて怖い。2つの大きな違いは、人がその場所でたくさん亡くなっていることだと思います。五百羅漢も、天命の大飢饉で何万人も亡くなって、100年200年かけて苔むすことで「死」を浄化してきた。これから災害の多い時代になるといいます。人口もどんどん減っていきます。そうすると、亡くなった人の供養もしきれなくなりますよね。大量の死者が出たときの供養や引き受け方の文化を失って、これから沢山の人が死んでいくことにどう耐えられるのか。一人の親しい人を供養すること、いきなりたくさんの人が亡くなる状況をどのように浄化して生きていくか、これからの弔いは、そういうことも考えていかなくてはならないと思います。
イベントの終盤、「これからどんな弔いの未来をつくっていきたいですか?」という100BANCH澤田の投げかけに対し、それぞれが描く「弔いの未来」が語られました。
前田:死と対峙して、自分が死ぬことを認識することで、どう生きるかを考えると思うんです。それがないと生きそびれてしまいます。死を通してこれから生きる人が自分の人生に向き合う形を作っていきたい。もうひとつは、血縁にとらわれない弔いの形を考えたいです。年に1回しか会わない親戚は家族葬に参列できて、毎週会う友達は参列ができないのは違和感があります。追悼サイトを作ったり、自宅葬を作ったり、選択肢を増やしたいです。
山本:弔いをする人が望む方法で弔える未来が来たらいいなと思います。そのために、個人個人の思う「弔い」を実現できる土壌を日本に作れたらいいと感じます。
鴻戸:私が作りたいのは弔うことがもっと身近になって、故人と共に生きれる未来です。今は「弔い」という行いが形骸化していて、形式的に「こなすもの」になっていると感じています。形にとらわれることなく、いろんな方法で故人を偲び、共に生きていくことはできるはずです。カードゲームで遊んだり、食べてみたり、日常の中でいつでも大切な人のことを思い出して、思い出とともに生きる身近な弔いが選択肢としてあふれる未来を実現できたらいいなと考えています。

前田の言うように、死に向き合うとき、私たちの中に、残りの人生をどう生きていくかという問いが生まれるのかもしれません。コロナ禍を機に100BANCHで死に関心を持つプロジェクトが増えた出来事は、これから自分たちがどう生きてゆくかを真剣に考える機運が高まっているとも言えるでしょう。
トークイベントの最後、赤坂さんは友人の編集者が詩集を出版し、記念パーティーをおこなったことを話してくれました。「元気なうちに大切な人たちを呼んで、明るくさよならをする。それも、ひとつの弔いの形だったのかもしれません」と振り返ります。弔いの未来を考えることは終わりではなく現在、そして未来の生き方を見つめることでもあるのです。
