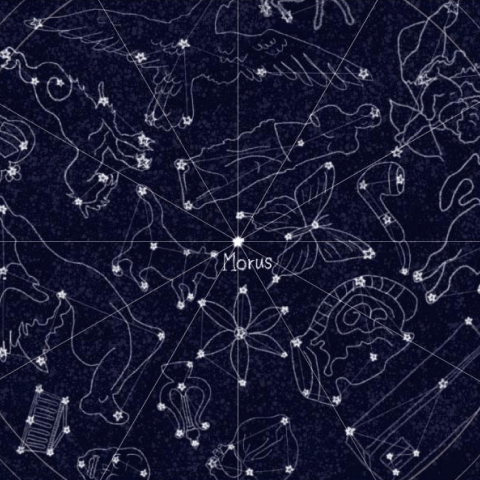
MUJO
渋谷で死と出会う
-
代表 前田陽汰


「人生はいつか終わる」。
あなたは普段からその事実を受け止めて生きていますか?
誰しもが必ず訪れる“死”なのに、それをあまり意識せずに毎日を過ごす人も多いのではないでしょうか。
「MUJO」プロジェクト(株式会社むじょう)のリーダー・前田陽汰さんは、私たちが避けては通れない死を日常に溶かす活動を通じ、死を忌み嫌う対象ではなく、生に活用する対象として捉え直す機会を与えてくれます。
なぜ死をテーマに活動を続けるのか。
「世の中の成長至上主義が、死や終わりを遠ざけてしまった」と言う前田さんに、 “死”をテーマに活動をはじめたきっかけや、現在の取り組み、そして未来における“死”へのあり方について伺いました。
——MUJOは“死”をテーマに活動をされていますが、そもそもこのプロジェクトは東京出身の前田さんが島根県の北に浮かぶ隠岐諸島・海士町(あまちょう)の高校に進学された経験がきっかけで始まったそうですね。海士町は、過疎化が進む町を独自の教育や観光の事業などで活性化させた、「地方創生のトップランナー」として知られる町です。
前田:僕はすごく魚釣りが好きだったので、毎日釣りができる環境が揃っている海士町の高校を選びました。正直、地方創生ってあまり興味がなかったので、それを横目にずっと釣りをしていて(笑)。島での生活の中で地元の漁師さんとか、民宿のおじさんやおばさんにお世話になっていたですが、そういう方たちって「地方を活性化しよう!」と意気込んでUターンとかIターンしてきた若者とは暮らしの温度が違うと感じたんです。

MUJOのリーダー・前田陽汰
——どんな違いがあるんですか?
前田:今を生き切ることに一生懸命であまり未来について語らない姿勢とか、息子が本土に家を建てても島には帰ってこないことを受け入れている姿勢とか、ずっと地元で暮らす人たちは、地域が緩やかに衰退していく未来を受け入れているというか。数十年後には誰も住んでいない未来が確かにあるのだけど、今そこで暮らす人たちは地域活性化しなければと切羽詰まっている状態ではないんです。私の解釈ですけど「活性化を頑張ろうと、今日の生活は変わらない。私たちは今日を生き切るのみだ」みたいな強さを感じました。
——ある意味で、諦めのような。
前田:諦めというより、今を肯定する考えなんです。決して活性化に向けて頑張っている人たちを否定はしないけれど、「いつか終わることは自然だよね」と思っている。結局、まちの活性化ってよそ者のエゴであったり、国が「地方創生をせよ」と号令を出したりして、「活性化すること=よいこと」という社会通年ができてしまったがゆえに、多くの人がその方向を向いているのであって、そもそもそれは長くその土地に住む人たちの意思ではなかったりするんだなって。それで、集落から人がいなくなったりするのは、そんなに悪いことではなく自然なことなんじゃないかと思うようになりました。

前田:海士町のように活性化を遂げたまちはメディアに成功事例として取り上げられる一方で、その流れに乗れない地域は「集落の消滅だ」とか、ネガティブなラベリングをされてしまう。でも、集落から人がいなくなるってことって視点を変えると、人が住むという集落の役割を果たしたとも解釈できますよね。
——その地では、人の営みをやり切ったというか。
前田:そう。でも社会は決してそうはさせてくれません。消滅しないように頑張って各地域で活性化を目指すわけだけど、それって少子化が進むなかで無理に人を奪い合うことでもあるから、幸せになる地域が生まれる裏で苦しむ地域が出てきてしまうんです。結局、全部が右肩上がりを目指すって不可能なんですよね。何かが終わることや人がいなくなること、役割を果たして淘汰されていくことも一つの選択肢として認められるべきだし、それがポジティブにとは言わなくても、ネガティブであり過ぎる必要はない。そういうメンタリティがないと、どんどん苦しむ人が増えていくんじゃないかなと感じたことがきっかけで、高校3年生のときに「ムラの終わりを考える」をテーマに集落での調査研究及び発信活動などを行うNPO法人ムラツムギを立ち上げました。
——ムラツムギは、まちの終活を通して地域住民の心の持ちようが変わるきっかけを提供する団体ですね。
前田:この事業を進めるうちに、まちを形成する人間の終わり方について興味を持つようになりました。お葬式とか葬送儀礼とか、いろんな文献を読んでいたら、これは面白いテーマだなって。それでムラツムギからスピンオフするかたちで、2020年5月に葬祭関連の事業を扱うMUJOを立ち上げました。
——MUJOというプロジェクト名は仏教用語の「諸行無常」から取ったと伺いました。世の中の全ての事象は常に変化するもので、永久に不変なものはない、という意味合いを持つ言葉です。
前田:MUJOは死や終わり、撤退や解散など終わりも一つの変化だと捉え、日々新しい物事が生まれては役割を果たして淘汰されていく世の中に対して、優しい眼差しを向けられる社会を目指しています。

——特に「死」にフォーカスされていますよね。
前田:先ほどの「まちが終わってはいけない」って意識もそうですけど、「終わりへの危機感の源泉はなんなのか?」と問い続けるうちに、人間が死から遠ざかったからではないか、と気付きました。何ごとも終わっちゃいけない、死んではいけない。際限なく右肩上がりの経済成長を目指さなくてはいけない社会、そして経済と共に発展してきた医療によって死を人間から遠ざけることに成功し、死や終わることへの免疫がなくなったと思いました。
——なるほど。
前田:でも僕は死や終わりから得られる幸せもあるはずだと思うんです。誰でも当たり前に迎える死という人生の締め切りを日常的に認識することで、今生きているという命に活かし、そして自分の人生を最後まで生き切ることができる。MUJOはそういった「死を日常に溶かす」というミッションを掲げてスタートしました。その後いろいろな事業を展開しているのですが、その一つに距離と時間を越えた3日限りの追悼サービス「葬想式」があります。
葬想式の解説動画
——葬想式は故人の思い出の写真やメッセージを投稿でき、公開期間中はいつでもどこからでもサイトにアクセス可能な、招待制の追悼サイトを作成できる無料サービスですね。2020年7月にスタートされました。
前田:MUJOを立ち上げる4カ月前に、自分の祖父が亡くなったんです。その葬儀で、祖父の若い頃の写真を見たり、祖父の友人から僕の知らない祖父の話を聞いたりして、「ああ、じいちゃんってこんな人だったんだな」って故人の新しい一面を知ることができました。そこからコロナ禍になり、葬儀社の対応が追いつくまでは日本中で葬儀を自粛するようになったのですが、コロナ前に比べてより死が曖昧になるなって感じたんです。
——曖昧、ですか?
前田:誰かが亡くなると、喪服を着て斎場に行き、芳名帳を書いて香典を渡して、みんなが悲しんでいる中、この前まで生きていた人が仏様になった姿を見る。そういう段階を経て人は故人の死を理解していくけれど、それが一気に抜け落ちると死んだという認識が曖昧になってしまうなって。人は葬儀の度に「人は必ず死ぬ」とあらためて認識してましたし、それが遠ざかることで自分が死ぬという事実すら忘れてしまう。葬想式は葬儀に立ち会えない親族や友人の弔いの機能はもちろん、そうやって故人の死から自分の生を実感できるものとしてサービスを開発しました。
——実際にどんな方が利用されていますか。
前田:例えばコロナ禍で海外の親戚の葬儀に行けなかった方や、身内のみで葬儀を済ませ、後々「お世話になった人がたくさんいたからみなさんとのお別れの場も作りたい」と思う方など、シチュエーションは様々ですね。また葬想式は参列者が他の参列者を招待できる機能があるので、故人の親族が知り得る友人や関係者から広がって、想像以上にたくさんの人が故人を悼む場所にもなります。現在も月に3件程の利用があり、都度改良を続けているところです。

——葬想式の開発後、MUJOは2020年10月に100BANCHのGARAGE Programに入居されます。プロジェクトメンバーには、アートによって病院にワクワクを取り入れる「PAIN PAIN GO AWAY」プロジェクトの中澤希公さんもおられますね。
前田:中澤さんとはNPO法人ETIC.が運営する起業家・イノベーター育成私塾「MAKERS UNIVERSITY」で出会いました。彼女はグリーフケアにまつわる活動をしていたので、死をテーマに活動する同志としてMUJOのメンバーに誘いました。今もですが、僕は外に出て交流することがあまり得意ではなくて、それを見た中澤さんから「もっと、いろんなところに出た方がいいよ。100BANCHはどう?」と勧められました(笑)。たしかに部屋にこもって研究するだけじゃなく、外に出なくちゃなって思っていたタイミングでしたし、ジャンルを問わず様々なプロジェクトが活動するGARAGE Programにも魅力を感じて応募しました。
——実際に100BANCHではどんな活動をされたのでしょうか。
前田:「死を日常に溶かす」というテーマをもっと具現化する活動をしていました。その一つが「棺桶写真館」です。これは参加者が実際に棺桶に入り、自身の死を体感することができる体験型展示イベントで、2021年10月に100BANCHの2階・GARAGEで開催しました。

《イベントレポート》
棺桶に入り、写真を撮り、自分の死をみつめる
MUJOプロジェクトが「棺桶写真館」を開催▷https://100banch.com/magazine/33488/
前田:棺桶写真館は「日常から排除された、誰しも当たり前に訪れる死に気付くにはどうしたらいいのだろうか」という問いから生まれた企画です。広島にある共栄さんという棺メーカーさんの工場見学に伺って実際に棺桶に入った時に、このまま火葬炉で焼かれることを想像したら「自分はまだ人生を生き切ってないな」という感覚が生まれました。それまでも死について考えていたはずなのに、身体を伴って死を意識する体験によってまた違う視点が生まれたんです。これをいろいろな人に体験してもらい、締め切りある命を認識することで生を実感してもらいたいと考えました。

——参加者は、棺桶に入る前に遺書を書き、人生を振り返りながら入棺を体験するだけではなく、その様子を写真に収めるんですよね。
前田:はい。写真を撮って他者に見せると何らかの反応が返ってくるので他者から見た自分の死を見つめることもできます。例えば「僕が死んだら、親はこんな気持ちになるだろう」というように、棺桶に入った自分の写真から、自分が死んだ後に遺された家族や恋人、友人側の視点も生まれるんです。
——客観的に自分の死を見ることもできると。棺桶写真館は、10代から60代までの約60人が実際に体験されたそうですが、この機会でどんな発見がありましたか。
前田:死は生に活用ができると感じました。死はどうしても避けられないと悲観するのではなくて、避けられないから残りの人生をどう生きられるかを考えられるなって。死をポジティブに捉えたいわけではないのですが、死をどう生の中に位置付けるかという問いに対して、「生に活用するもの」という暫定解を得られる機会になりました。
——100BANCHの他プロジェクトのメンバーやPS(プロジェクトスタッフ)も実際に棺桶に入る体験をされたそうですね。
前田:棺桶写真館の準備中にいろいろな人たちが興味を持ってくれました。それまで僕は直接コミュニケーションをする場をつくったことがなく、葬想式の説明会もZoomで開いたし、プロモーションもメディアを使ったし、どうやって事業を広げていこうかって時もSNSの戦略を考えたりして。そういう方法が得意だからってことはあるんですけど、棺桶写真館をオフラインで開催して、自分には「直接、参加者と会っちゃおう」って発想が抜け落ちていたんだなと思わされたというか。今回、100BANCHという場所を活用させてもらい、目の前の参加者が見せる表情の移り変わりや、さりげなく聞こえてくる声など、現場でしか得られない空気感に触れたことは僕にとってすごくありがたい経験になりました。
——MUJOは、今年の4月8日〜5月8日に天国への想いが集う、母の日の特別展示会「死んだ母の日展」を開催されました。これは母の日に合わせ、亡くなった母への手紙をインターネット上に匿名で投稿できるサービスですね。

前田:この展示はメンバーの中澤さんの実体験が元となりスタートしました。中澤さんは中学生の頃に母を病気で亡くし、母の日になると、もう母にはプレゼントを渡すこともできないし、自分だけが周りから取り残され、ひとりぼっちのような気になったと打ち明けてくれました。それで「母の日にはカーネーションを贈る」とか社会的に商業化された母の日によって、取り残されている人がいることに気付かされました。この現状から、親を亡くした人の父の日・母の日の過ごし方の選択肢をつくりたいと思い、この展示の構想が生まれました。その頃、父の日が近かったことから、昨年(2021年)6月に「死んだ父の日展」を開催し、そこでは約440通の亡き父への手紙が集まりました。
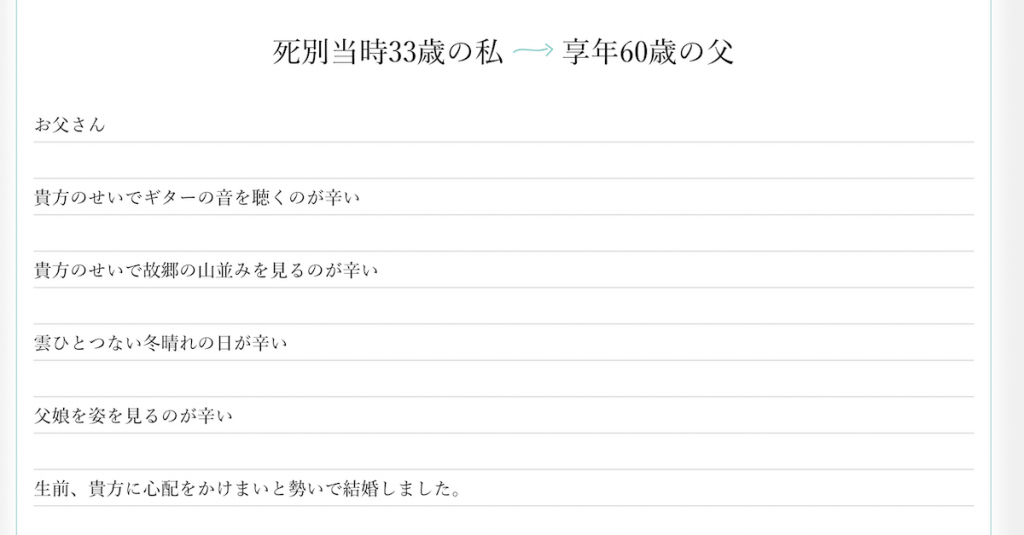
前田:参加者から「父がいない側に気付いてくれてうれしかった」という声を聞いて、父の日のように誰かにとっては喜ばしい日でも、誰かにとってもつらい日になることって顕在化していないだけで、世の中にはたくさんあるのだとあらためて気付かされました。他にも「この展示のおかげで、父への想いの行き場ができた」という声や「母の日にもやってほしい」という人もいたことから、今年は死んだ母の日展の開催を決めました。今回の展示には、8社の葬祭関連会社様に協賛をいただきました。ゆくゆくは葬儀業界が主体となって実施する企画にしたい考えています。

——棺桶写真館、死んだ母の日展など100BANCHでの活動を経て、これからどんな取り組みをされる予定でしょうか。
前田:実は葬儀屋をやろうと思っていて。
——MUJOが、ですか!?
前田:はい。葬想式や棺桶写真館、死んだ母の日展を開催してみて、やっぱり故人や遺族と最初から最後まで接点を持っていろんなお手伝いをするのは葬儀屋だと思ったんです。葬想式や死んだ母の日展は葬儀屋に活用してもらえるサービスでもあるのですが、従来のやり方との兼ね合いでうまく活用いただけない部分があったんですね。それだったら僕たちが開発するサービスをフル活用した新しいお別れのかたちを葬儀として提供したいと。
——自分たちの発想を持ち、死に対してアプローチしてと。今までにはないお別れのかたちが増えていきそうですね。では最後に、前田さんが思い描く100年後の未来像を教えてください。
前田:最初の話に戻るのですが、ムラツムギやMUJOの延長線上に、死ぬとか終わるとか、撤退するとか解散するとか、そこにあるなんとなく触れづらいテーマがもう少し語りやすくなり、その側面にもちゃんと光が当たるような世の中になればいいなと思っています。そして僕たちの取り組みがある意味で、成長至上主義へのアンチテーゼになればいいなと。僕は海士町での高校生活で、「過度な成長の先に幸せってあるんだっけ?」とか「終わることってそんなによくないことなんだっけ?」とか、そういう問いに良くも悪くもとらわれてしまったんです。
——たしかに業績が上がったからと言って、関わる全ての人が幸せになるとは限りませんからね。
前田:そうなんです。人ってどこまで成長すれば幸せなのかって。例えば大企業はどこまで時価総額を上げたらいいのか。その答えって「上げ続けなきゃいけない」じゃないですか。でも、成長し続けることには苦しみも伴いますし、盲目的に成長を目指すと目的を見失ってしまう。株主資本主義ってその最たるもので、どのタイミングでも株を持った人には利益をもたらさなきゃいけないので、会社は絶対に成長し続けないといけない。そういう構造だとソフトランディングする術はないし幸せって尺度もないから、成長一辺倒を問い直し、終わりゆく変化に優しいまなざしを向けるという選択肢があまりにもないんです。だからその流れを見直せる機会を作り、「成長する・しない」、「右肩上がり・右肩下がり」だけじゃなくて、「業績は右肩上がりだけど、こんなの幸せじゃないよね」とか、「右肩下がりだけど納得感を持って終わってもいいよね」とか、そういう意識が生まれていったらいいなと思います。

(写真:小野瑞希)