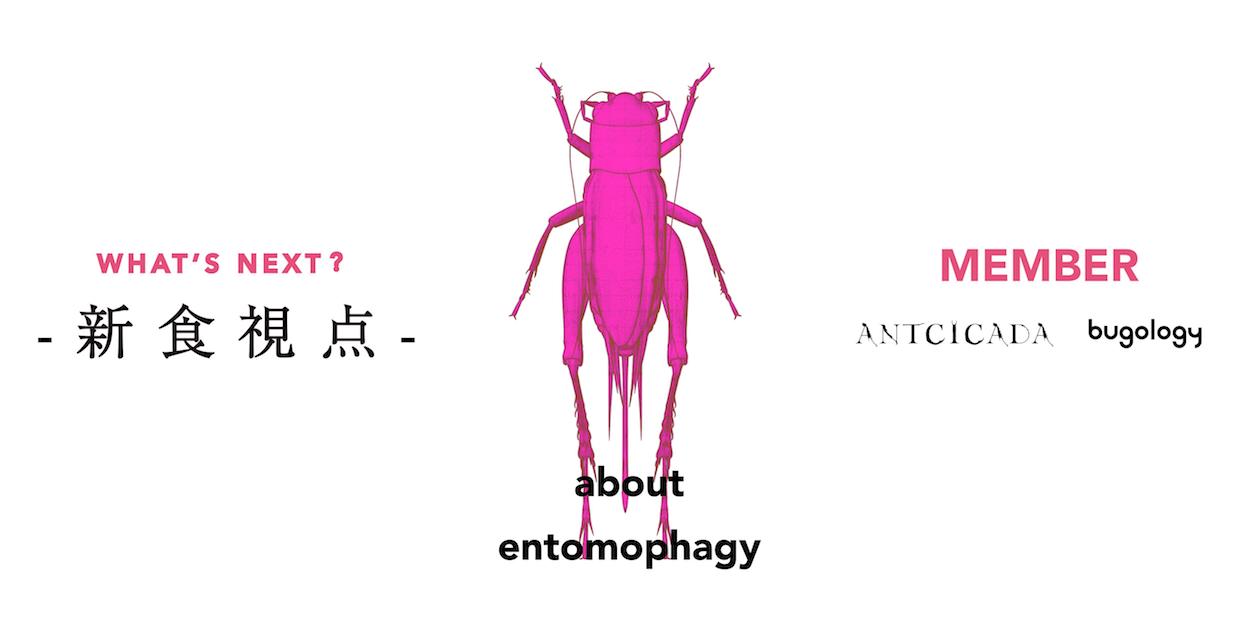
WHAT’S NEXT? -新食視点-

「虫を食べる」という行為について、貴方はどう感じますか?
「全然大丈夫」という人より、「ちょっと、いや、かなり抵抗があるな……」と思う方のほうが、おそらく多いかと思います。
でも、それは一体なぜでしょうか?
「虫は食べものじゃないから」――決してそんなことはありません。日本では珍しいかもれませんが、現状でも世界では約1900種類もの昆虫が食べ物として扱われていて、20億人以上がそれらを食べて生活しています。
「それでも、虫を食べるなんて普通じゃない」―—確かに、現在の日本ではあまり普通ではないかもしれません。けれども一昔前にさかのぼれば、日本でも日常的に虫が食べられていた記録は、至る所に残っています。時の流れと共に「普通」は変わるものです。今だって、長野県や岐阜県などを中心に、イナゴや蜂の子を佃煮などにして、日常的に食べている地域は存在します。
世界規模で増え続ける人口に対して、食糧生産が追い付かなくなってきている昨今、「昆虫」は貴重な食糧資源として注目を集めてきています。100年後の未来では、「肉」「魚」「野菜」といった食材のジャンルに、当たり前に「昆虫」が並んでいるかもしれません。
……「昆虫」が当たり前に食材として受け入れられるようになった未来の社会では、どんな昆虫食が存在していると思いますか? 罰ゲーム的に扱われるような認識を乗り越えて、料理として、文化として純粋に洗練されていった先の「ムシ料理」は、一体どんな進化を遂げているのでしょうか?
そんな未来のムシ料理を味わえるイベント「WHAT’S NEXT? -新食視点-」が、先日100BANCHで行なわれました。本記事では、このイベントの実食の感想も合わせたレポートを“昆虫食が当たり前になっている未来の食レポ”風にお届けします。
Bugologyダイジェストムービー(directed by bugology & yago)
2050年、“食べる”という行為は私たちにとって、未だに切っても切り離せない日常だ。十数年前まで、世界中が食糧危機に陥っていたことは記憶に新しい。そのおかげで人工的なエネルギー源の培養技術が飛躍的に発達し、生きていく上で必要な栄養の補給ならば、安価なサプリメントとゼリー飲料でほぼ完璧に“摂取する”ことが可能になった。
そんな昨今において、自然な食材を用いた料理を“食べる”ことは、比較的高くつく道楽と言ってもいいだろう。それでも統計上の現代の日本人は、少なくとも週に数度は自炊もするし、外食もしている。時間と手間、お金をかけて、わざわざ“食べる”ことを選んでいる。

なぜ、私たちはこれほどまでに食に固執するのだろうか――最近、その理由の片鱗を感じさせてくれる店にめぐり合えた。渋谷某所、繁華街の喧噪から少し離れた川沿いに佇む、とあるムシ料理店だ。
この店のオーナーたち――ANTCICADA代表の篠原祐太とbugology代表の高橋祐亮は、今から30年ほど前、ちょうど東京オリンピックが開催されていた2020年あたりから、この地で昆虫食の普及に努めていた2人だ。今や家庭でもレストランでも、安定的に安く手に入る自然食材として欠かせない昆虫だが、当時の日本では養殖方法や調理法が確立されていなかったこともあり、ほとんど“食べもの”として認識されていなかった。にわかには信じがたいが、昆虫を食べることが「気持ち悪い」とすら思われていたそうだ。
昆虫食が非日常だった時代から、食材としての昆虫の可能性を追求し続けてきた二人。それが日常に溶け込んだ今、彼らは料理として、そして体験として洗練された「これからの昆虫食のスタンダード」を模索していた。

いま、町を歩けば所々にムシ料理店が目に入るが、その多くは大衆的な屋台風であったり、ファストフード的な印象が強いだろう。また、これらが一般的になる前までは、ムシ料理店と言えば前衛的な高級レストランが大半だった。
しかし彼らがプロデュースしたこの店は、どちらのムシ料理店のイメージとも一線を画している。カジュアルでありながら、どことなく上品さが漂う店内。チープにもラグジュアリーにも寄らず、どんな用途でもフィットしそうな空間から、彼らが掲げる「昆虫食のスタンダードのど真ん中を目指す」というコンセプトがひしと伝わってくる。
数あるメニューの中から私がオーダーしたのは、シェフからのオススメ印の付いた「-新食視点-」と題されたセット料理だ。特製ドリンクに小皿料理がデザートを含めて4品、そしてメインディッシュにラーメンが提供される。

「飲み物の容器」作品タイトル「sapia(樹液(sap)のある場所(接尾辞の-ia)をあらわした造語)」
まずドリンクから驚かされた。茶筒を重ねたような中身の見えない木製の容器と、鉄製のストローが目の前に置かれる。どうやらその中に飲み物が入っているようで、容器には4つの穴が空いている。なるほど、この穴にストローを差し込むのだなと想像はつくが、いざ差してみると、手前の方で木の壁に阻まれている感触のある穴もある。つまり、「飲める穴」と「飲めない穴」が存在するのだ。
「セミの食事の様子をモチーフにしてつくりました」と、この容器をデザインした高本夏実さんは語った。セミは細長くとがった口を、木に突き刺して樹液を吸う。刺しどころが悪ければ、うまく吸えないこともあるだろう。そうした昆虫の食事行為を、昆虫食のフォーマットの中で追体験することで、自然な環境下で本来存在するはずの――現代の社会ではブラックボックスに隠されてしまっている――「“食べる”に至るまでの苦労」を、小さいながらも久々に味わえた気がした。

「4連結の小皿」作品タイトル:monocuspis-decacuspis(cuspis(ラテン語:尖)mono(ラテン語:1)deca(ラテン語:10))
続いて4つの小皿で運ばれてきたのは、生春巻き仕立てのサラダ、ギョーザ、卵かけご飯、わらびもちだ。この小皿も「昆虫料理の多様な未来に対応する」というコンセプトから、デザイナーの風祭あゆみさんがオリジナルでつくったものだ。
それぞれの料理についても、見た目にはそこまで存在感のないものの、昆虫がふんだんに使われている。
生春巻きの中にはクリーミーな蜂の子が入っていて、上に乗せられたツムギ蟻の酸味が香辛料として効いている。ギョーザの種は豚とセミの合い挽き肉が使われており、ナッツを感じさせるような余韻のあるコクが後を引く。
卵かけご飯の卵は、大豆ではなくコオロギ麹を発酵させてつくった「コオロギ醤油」に漬け込んだとのことで、独特な滋味がある。そして、デザートのわらびもちは、桑の葉を食べて育つカイコのフンが練り込まれているからか、ほのかにハーブのような爽やかさを感じた。
これらの小皿料理は「昆虫食のスタンダードのど真ん中」という意気込みの通り、日常的な料理の中で、昆虫がそれぞれの“らしさ”を味の個性として発揮しながら、ほかの食材と共存できることの、確固たる証明のように感じられた。

コオロギラーメン(シェフ:篠原祐太)
極めつけは、メインディッシュとして提供された、コオロギラーメンである。出汁からカエシ(醤油ダレ)、麺、香味付けの油に至るまで、すべてにコオロギがたっぷりと使われている逸品だ。
シェフである篠原曰く、このラーメンの出汁には「大地を思わせるような香ばしさと旨味のある」フタホシコオロギと、「たんぱくで上品な味わいとまろやかな甘味を持つ」ヨーロッパイエコオロギをブレンドして用いているそうだ。この組み合わせにたどり着くまでに、世界各国のさまざまなコオロギを食べ比べ、配合を徹底的に研究したという。
一口食べて、衝撃を受けた。ラーメンには「家系」「鶏白湯」など味の系統として確立されたジャンルがいくつかあるが、そのどれにも被らない「コオロギラーメン」という独自の美味しさが、そこには歴然と存在していた。
少し前まで「エビのような風味」と語られることも多かったコオロギラーメンだが、あっさりと澄んだ口当たりの先で力強く主張してくるこの一杯の旨味は、ほかの何にもたとえ難く、それは「昆虫はそれぞれが食材としてオンリーワンである」というつくり手たちのメッセージのようにも感じられた。

——以上が、彼らの店で食べたものの、率直な感想である。食事として満足感のある内容であったことはもちろん、“食べる”という行為についてのインスピレーションをかき立てられる、エキサイティングな体験であった。
とりわけ整備の行き届いた都市部に住む人間にとって、「生物」と「食材」の乖離は激しいものだ。肉や魚などの食材が生きとし生ける存在であったことを、知識ではなく肌で感じる機会は、日常の範囲にほとんど残されていない。
しかし、昆虫はほかの食材と比較すれば、よっぽど身近だと言える。目視できる自然な存在である彼らを、わざわざ“食べる”という体験には、私たちに「ほかの命をいただいて生きている」という感覚を取り戻させる力がある。その感覚が欠落しつつある今の世界に、もっと危機感を覚える必要があるのではないだろうか。
「飽食」から「無食」へと移り変わる今こそ、私たちは昆虫食を通して、再び「生き物としてのリアル」に立ち返らなければならない——そんな一連の思考を誘い出してくれた彼らの店に、あらためて感謝したい。
……と、唐突な未来設定でここまでお送りしました。読者の皆様、お付き合いいただきありがとうございます。
冒頭にも少し触れましたが、上記の実食レビューで言及している食べ物は、2019年7月7日に100BANCHで行なわれたイベント「WHAT’S NEXT? -新食視点-」で提供したものです。きっと今後、同じものや、さらにアップデートされた料理が食べられるイベントが企画されるはず。皆さんにもぜひ一度、実際に食べてみて、何かを感じてもらいたいなと思っています。
イベントの主催者であるANTCICADA代表の篠原祐太と、bugology代表の高橋祐亮は、料理提供後のトークセッションで、それぞれ次のように語っていました。

篠原「私たちは地球が大好きです。そして、その地球上に生きる命に“優劣”も“ゲテモノ”もないと思っています。人も、動物も、植物も、虫も、同じ地球を共に生きる身として、分けへだてなく愛したい。肌と肌でふれあいながら、地球からの贈り物を五感で味わい、その魅力を提案したい……そんな思いを胸に、昆虫料理の可能性を探っています。
食体験は、驚きや発見に満ち、悦びに溢れているものです。食することで生き物と一つになり、繋がっていく。私たちANTCICADAは昆虫料理専門店として、昆虫食の素晴らしさを伝えると共に、人の視点や価値観を拡げるきっかけをつくり続けたいと考えています。地球を味わうワクワクを、皆さんと一緒に分かち合っていきたいです」

高橋「僕らはbugologyというプロジェクトを通して、昆虫食の魅力を適切な出力――昆虫料理のレシピのアーカイブ、昆虫食にまつわるプロダクトの開発、そしてこれらを広めていくイベントの3要素で広めていきたいと考えています。今回のイベントでは、この3つの要素をすべて盛り込んでみました。
昆虫食は新たな“食文化”として、料理だけに留まらない多彩な可能性を秘めています。新しい調理法やテーブルマナー、食器、見せ方といった周辺の可能性を同時に開拓しながら、それらの過程をアーカイブしていくことは、ひとつの“歴史づくり”に他なりません。これからも、そんなダイナミックな営みに参加できることを楽しみながら、昆虫食への参加障壁を下げ、多様な発展を促進していけるような取り組みができればと思っています」
***
ひとつの「当たり前でなかった」文化が、「当たり前」になっていく歴史を、私たちはこれから目撃できる――そう捉えると、なんだかワクワクしませんか? 皆さんぜひ、これから昆虫食の動向、そしてANTCICADAとbugologyの活動、活躍に関心を持ってもらえたら幸いです。
(写真:鈴木渉)