記憶の主権を人からモノへ。思い出が日常空間に編み込まれる社会を実装する。

yomiyomi
記憶の主権を人からモノへ。思い出が日常空間に編み込まれる社会を実装する。
-
yomiyomi リーダー 仲村怜夏


美味しいものを食べるとき、友だちと飲みに行ったとき、かわいい犬や猫に会ったとき……。あなたはどんなときにスマホで写真を撮りますか? 撮っただけであまり見返さない人も多いのではないでしょうか。写真や動画を残すことが簡単になる一方、改めて「写ルンです(カメラ付きフィルム)」やフィルムカメラの価値が見直されているのは、「思い出や記憶をきちんと残す」ことの難しさ、貴重さが浮き彫りになっているのかもしれません。
「20歳の誕生日から毎年『1年後に死ぬとしたら何をしたいか?』とリストアップして、24歳のときに『日本で誰もが知っているようなプロダクトをつくりたい』と記したんです」。そう語るのは、「yomiyomi」のプロジェクトリーダーを務める仲村怜夏。そのリストに記した通りにデザイナーとなり、フラワーアーティストの活動をはじめ、2024年夏に新たに始動したのがyomiyomiでした。
yomiyomiは現代における「記憶」のあり方を問い直すプロジェクト。「記憶の主権を人からモノへ」をテーマに、スマホをかざすだけで思い出がよみがえる「思い出召喚ステッカー」を開発し、記憶を「人に依存するもの」から「モノを媒介に循環するもの」への転換を試みています。2025年7月の100BANCH入居以来、清水建設など企業とのコラボや「Tokyo Innovation Base(TIB)」への採択、「グッドデザイン・ニューホープ賞」入選など快進撃を続けるyomiyomi。それを率いる仲村は、どんな未来を実装しようとしているのでしょうか。
──「yomiyomi」ってポップな名前ですよね。どんな意味が込められているんですか?
仲村:元々、暫定案で付けていたんですよ。『ONE PIECE』のブルック推しなので、「ヨミヨミの実」って語感がいいなと思っていて。そうしたらみんな「データを読み込んだら記憶がよみがえるから『yomiyomi』なの?」って良い感じに解釈してくれたので、そのまま正式名として採用しました。
──私も「よみがえるから『yomiyomi』なのかな?」と思っていました。
仲村:そうなんです。最初は軽い気持ちだったのですが、今となっては大切な名前ですね。

──プロジェクトを着想されたのはどんなきっかけだったのですか?
仲村:小学生の頃に祖父母を亡くして、「人はいつか死ぬんだ」と実感したのと、やはり19歳のときに父を膵臓がんで亡くしたのが大きかったですね。特別仲が良いわけでもなかったので、あまり写真も残っていなくて。母も乳がんになりましたし、自分もずっと健康で生きていけるわけではなさそうだな……というのを実感するようになって、何かをやり残して死んだら私、霊になって出てくるんじゃないかって(笑)。それで20歳の誕生日から、「1年後に死ぬとしたら何をしたいか?」とリストアップする習慣をはじめたんです。22歳のときは「デザイナーになる夢をあきらめたくない」、23歳のときに「自分の思想を形に残すことで、生きた証を未来へ残したい」とフラワーアーティストとしての活動をはじめて、24歳のときに「日本で誰もが知っているようなプロダクトをつくりたい」と、このyomiyomiを立ち上げました。
父の死から5年も経ってからだったのは、あまりに大きな出来事で、人に伝えられるくらい消化するまで時間がかかったんだと思います。ぼんやりと「記憶や思い出を残したい」と思っていましたが、「今日の思い出を、一生のお守りに。」というコンセプトとして言語化できたのは、このプロジェクトをはじめてからでした。
──そうした経験から「記憶を残す」ということへの強い動機が生まれたんですね。プロジェクトページにある「記憶の主権を人からモノへ」という言葉も印象的です。
仲村:人には卒業式とかイベントとか、忘れたくない瞬間がたくさんあると思うんです。ただ、スマホで誰でも簡単に記録を残せるけど、あまり見返されることもなく埋もれてしまう。そもそも私がいなくなってしまったら、何がどこにあるのかもわかりませんよね。いつ死ぬかわからない中で、自分自身や自分の大切な人が生きた証を物理的に次世代へ残すにはどうすればいいんだろうと考えたところ、たどり着いたのがNFCの技術を使って動画を残すことでした。記憶を「人に依存するもの」から「モノを媒介として循環するもの」に変えることができたら、記憶がモノを通じてずっと残りつづける世界になるんじゃないか、と。動画という媒体にこだわったのは、記憶から真っ先に抜け落ちていくのが「声」とか「仕草」とか、そういう何気ない瞬間だと思ったからです。
──100BANCHには4回応募されて、ようやく採択されたと聞きました。
仲村:yomiyomiを2024年6月頃に立ち上げて、すぐに応募したのですが全然ダメで……最初はスライド1枚くらいの資料しかなかったんです。元々所属していたゼミの先輩には100BANCH出身の方が多くて、面白い人ばかりで、私にとってはキラキラしたコミュニティに見えたんです。だから自然と「私もそこに属したい」と思って、大学時代からの友人を中心に声をかけて、メンバーを集めました。プロダクトの世界観や明確なビジョンというよりは、「なんかデカいことやろうぜ!」みたいな感じで呼びかけたことにワクワクしてもらえたのかなと思っています。私自身、結構「猪突猛進型」なのですが、集まったメンバーはある種淡々と物事を進めていける人、ちょっと俯瞰してフィードバックできる人……みんな自分にないものを持っていて、すごくリスペクトしています。
自分の中にある思想そのものには自信があったのですが、さすがに応募3回目でダメだったときは仕切り直さなきゃいけないな、と。思想や世界観をちゃんと形にしなければ伝わらないんだと思って、そこから1年くらいかけてプロダクトを開発してプレリリースして、実際に使ってもらうところまでしっかり手を動かしていきました。4回目でやっと採択されたときにはすでにローンチイベントの開催が決まっていたので、毎日100BANCHに通って作業をさせてもらいました。しっかり助走期間があったからこそ、いろんな実績につながってきたんだと思います。

──第1弾プロダクトの「思い出召喚ステッカー」はどのようにして生まれたのですか?
仲村:「スマホでICタグを読み込むと思い出がよみがえる」という機能は当初からあったものでした。ただ、プロダクトとしては元々お花とセットにしていたんです。フラワーアーティスト(フラワーショップポアダム)としても活動しているので、ドライフラワーのブーケにして「枯れない花に記憶を宿す」みたいな形で展開できたら、と。ただ、いろんな方にヒアリングしていく中で、「花は用途が限られるから、いろんなものに記憶を宿す形にできないか?」といったフィードバックをいただいて。それで考えたのが「ステッカー」でした。

第1弾プロダクト「思い出召喚ステッカー」。スマートフォンをかざすだけで、動画メッセージを保存・再生できます。メールアドレスを登録すれば1年後にリマインドメールが届く仕掛けも。
──ステッカーなら、toCプロダクトとしても展開できそうですが、toBプロダクトとしてプレリリースされたのは戦略的な考えだったのですか?
仲村:戦略というよりは後ろ向きな理由なのですが、私自身がSNS戦略を考えるのが苦手で。不特定多数に向けてアプローチするより、特定の企業のために提案するほうがお互いにハッピーだなと考えて、まずはtoBからはじめることにしました。実際、「CHOOSE YOUR LIFE FES」とのコラボでは、「人生のお守りになる一日を」というコンセプトのフェスだったので、「『今日の思い出を、一生のお守りに。』というyomiyomiのコンセプトとも合致していますよね?」とプレゼンして、採用してもらえました。「リマインドメールが届く」というのもプロモーションとして有効だと評価をいただきました。その後、他社の方からのお問い合わせも増加したため、実績としてはかなり大きかったです。
──確かに、フェスだと毎年同じ時期に開催されることが多いですもんね。
仲村:何より「デカいことやろうぜ!」ってメンバーを集めましたしね。カルチャー好きなメンバーが多いので、「Zeppで開催されるイベントがプレリリース第1弾ってヤバくない!?」とチーム全員でワクワクしながら準備をしました(笑)。実現できて良かったです。

──他にも企業とのコラボが実現していますが、どういった点が評価されているのでしょう?
仲村:いちばんはコンセプトや世界観に共感していただいているのが大きいのですが、次に大きいのはデータ活用の点ですね。サービス利用にあたってユーザーの承諾を得られる形にしているのですが、実際に撮影してもらった動画を再利用したり、リマインドメールをチケット販売開始のタイミングで送ったりするなど、企業側がプロモーションなどに活用できるようにご提案しています。また、どういったユーザーがどのタイミングでプロダクトを利用しているのか、といったデータも共有できるので、ユーザー理解にも役立てていただけるのかな、と。私自身、デザイン会社で3年働いてきて、企業向けに具体的な提案をする機会も多く、どれだけ思想や価値観に共感していただいても、上長の決裁をいただくには具体的な数字やデータが重要だというのを痛感してきたんですよね。ですからご担当者には「どんなデータがあれば社内的に評価してもらえそうですか?」とヒアリングして、できる限りそのニーズに応えるようにしています。
──「死」という個人的な体験がきっかけでありながら、すごく普遍的なプロダクトになっているのは、そうした俯瞰的な視点も影響しているのかもしれませんね。
仲村:自分の思想をどこまで反映してプロダクトをつくるのか、というのは悩みどころではありましたが、とにかく「日本で誰もが知っているようなプロダクトをつくって死ねたら、本望だな」と思って。だから自分の思想を前面に出すより、まずは「かわいい」とか「便利だな」とか何気ないきっかけで手に取ってもらえたら良いな、と。その上で誰かがしんどいとき、人生のお守りにしてもらえるようなプロダクトをつくりたいなと思ったんです。
100BANCHでは、実験報告会などのイベントで先輩方の「思想を信じつづけている」「色々あるけど、なんとか生きてこられた」みたいな話を聞けて、すごく勇気づけられるんです。プロジェクトを進めていく中で、妥協しなければならない場面もあるけど、本当に大切な部分は譲らない。そういうブレない軸を貫いて実績を残している先輩たちの姿を見ていると、未来に期待が持てるというか、根拠はないけど心強いなと感じます。

──それにしても、会社でデザイナーとして働きながら、フラワーアーティスト、yomiyomiと複数のプロジェクトを並行しているのは、どんなモチベーションがあるのでしょう?
仲村:何か正義感に駆られてというより、もっと単純に同世代や周りの人に対する憧れというか、「ヤバい、このままだと“すごい人の友だち”みたいなダサいポジションになるぞ!?」みたいな、嫉妬と憧れの混じり合った感情が動機になっているかもしれません。「起業してお金を稼ぐ」みたいな野心はそんなになくて、「カルチャープレナー」「クリエイティブアントレプレナー」と呼ばれるような方々……自分の信じる思想をブランドとして提示する人たちに憧れてきたので、なんとかそれに近づきたいとしがみついている感じです。
それにわりと早いタイミングで「死」という莫大なエネルギーが動く現象を意識するようになったのは、良くも悪くも大きかったと思います。
あとは……単に「憧れ系」というのもありますね(笑)。ミュージシャンやお笑い芸人さんが好きで、彼らみたいに夢を追ってキラキラしている人になりたいな、って。そもそも今勤めている株式会社ゆめみに入社したのも、「学生時代から積極的に活動して……」みたいなポジティブな意味合いではなかったんです。父を亡くして、私自身も体調を崩してしまったり家庭の事情が重なったりで、大学在学中、卒業単位が足りていない中、なんとか働くところを見つけないと生きていけないなと思って。いろんなデザイン会社にポートフォリオを持っていったのですが、ゆめみからは「大学はまた戻れそうなときに戻れるかもしれないし、東京にはいろんなチャンスがあるよ」と言ってもらえて。それで大学を休学して第二新卒扱いで入社して、働きはじめて3年目になりました。
──ローンチイベント、企業コラボ、ピッチコンテストへの参加など、yomiyomiとしてはかなり順調に活動されていますが、ご自身としてはどう評価されていますか?
仲村:自分の過去と比較するとうまくいっているかもしれませんが、今と未来を比較するとまだまだだなって感じですね。1つ壁を越えたらまた別の問題が見つかった……みたいなことが毎日起こっています。「SNS戦略が苦手」みたいなのも明確に見えている課題だし、まだまだ頑張らなきゃな、って。でも、とりあえず辞めなければどうにかなるかな、と思っているんです。飽き性で「辞めない」のは自分にとっていちばん難しいことだから、どこまで行けるのかはわからないんですけど……「辞めないぞ」という強い気持ちだけは持っています(笑)。
最近よく言っているのは、「『忘れたくない日の記憶』が日本一集まっているプラットフォームをつくろう」と。それを実現したら、その向こうに「日本の誰もが知るプロダクト」が見えてくる気がする。とはいえ、自分たちの思想にウソをつかず、「でっかいことやるぞ!」というのが、根底にあるテーマではあります。
──yomiyomiとして、これからどんなことを実現していきたいですか?
仲村:葬祭用具メーカーの三和物産さんと死生観を問う「死ンキングナイト」というイベントでご一緒したのもありましたが、私自身、人生について考えこむことが多いので、ライフステージに寄り添うプロダクトをつくれたらいいなと思っています。誕生、入学卒業、就職、結婚、子育て……終わりを迎えるまで、その時々できちんと寄り添う存在でありたいと思いますし、関連する事業者さんと協業してみたいですね。
それと、元々ステッカーだけにこだわっているわけではないので、新たな展開ができたら良いなと思っています。清水建設さんとのやり取りの中でもお話ししたのですが、建物に記憶を宿したら、新しい価値が生まれるのではないか、と。清水建設さんは、建築分野のインキュベーション・プログラム「ASIBA」を通じてご紹介いただいたのですが、はじめはステッカーだけだとシナジーが生まれにくいのではないか、と懸念をいただいていたんです。それで改めてプレゼンするとき、「建物や建材に記憶を宿す」構想をお話ししたところ前向きに検討いただいて、思い出召喚ステッカーをノベルティグッズに実装することになりました。他にもまちづくりや都市開発に関連する企業との協業を進められたら、色々と実現できそうなことがあるのではないかと考えています。
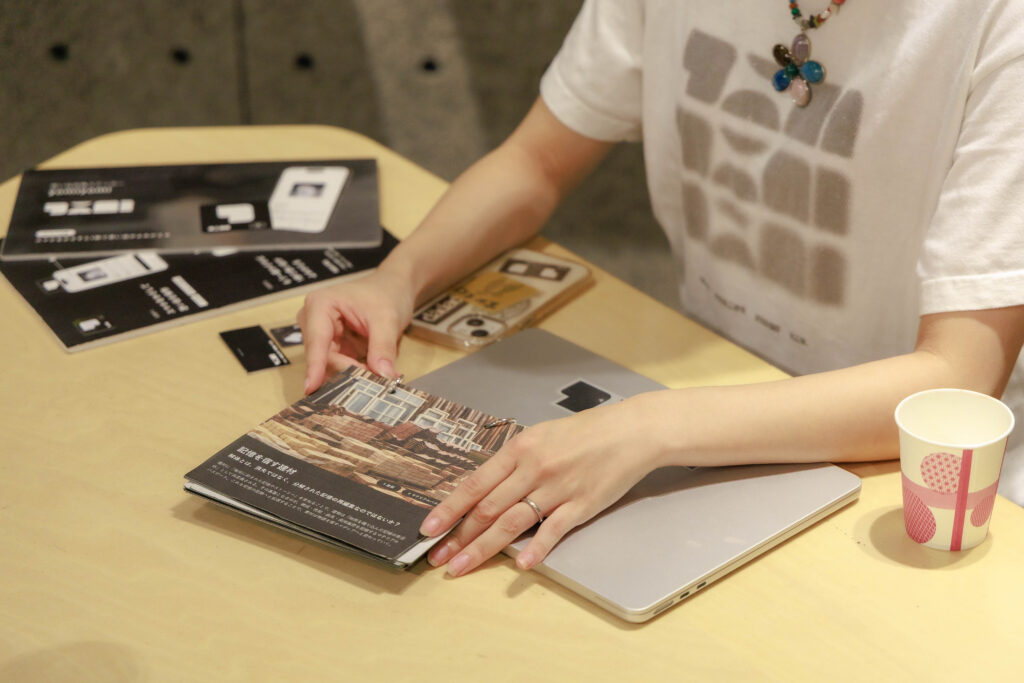

──「建物に記憶を宿す」というのは、壮大なビジョンですね。
仲村:例えば机に記憶が宿っていて、前に使っていた人の思い出を知ることができたらめっちゃ面白いんじゃないかなって。それこそ建物をつくっていた人の想いが伝わってきたら、その建物の使われ方も変わるかもしれない。「モノに記憶を宿す」というアプローチは、これまでの記録の歴史に対する新しい提案だと思うんです。口伝から絵になって、文字、写真、そして動画になって……長い歴史の中でずっとなんらかの形で伝えられてきたものがあって、それがなかった時代にはもう戻れない。それくらい「モノに記憶が宿ること」が当たり前になって、誰もが自然に記憶を辿ることができたらいいなと考えています。
──日本では「万物に魂が宿る」考え方も馴染みがありますし、yomiyomiのビジョンに共感する人も多いかもしれません。
仲村:ありがとうございます。今って、SNSを通して簡単に人とつながることができるけど、逆に強く孤独を感じる人が多い時代だと思うんです。だからそんなとき、人の暖かさをちゃんと実感できるようなものがつくれたらな、って。
プロダクトだけにとらわれず、アート作品も開発して、記憶のあり方自体を問い直していきたいとも考えているんです。ローンチイベントでも展示した「yomi dB camera(ヨミデシベルカメラ)」という作品は、その空間のデシベル(音の大きさ)を判別して、大きな歓声や笑い声が起こった瞬間をキャプチャーして、レシートに印刷するんです。
SNSって、カメラや人を意識した「キメ顔」しか残らないじゃないですか。でも、それって私たちの本当の表情なのか?と疑問に思っていて。 だからもっと何気ない瞬間を切り取ることができたらなと。yomiyomiにはアート分野やアカデミアに通じているメンバーもいるので、それぞれの強みを活かしながらビジネスと実験の両軸で様々なことを実現していけたらいいなと考えています。

(取材・執筆:大矢幸世)