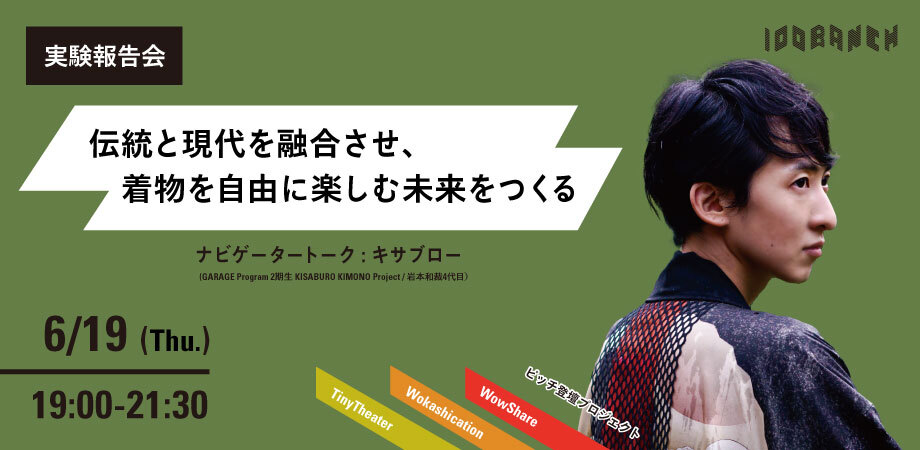
「伝統と現代を融合させ、着物を自由に楽しむ未来をつくる」100BANCH実験報告会

100BANCHで毎月開催している、若者たちが試行錯誤を重ねながら取り組んできた“未来に向けた実験”を広くシェアするイベント「実験報告会」。
これからの100年をつくるU35の若手リーダーのプロジェクトを推進するアクセラレーションプログラム「GARAGE Program」を終えたプロジェクトによる100BANCHでの活動報告や、100BANCHでの挑戦を経て、プロジェクトを拡大・成長させた先輩プロジェクトによるナビゲータートークを実施しています。
2025年6月19日に開催した実験報告会では、着物を通じて国境や性別などあらゆるボーダーを越え、全ての人々を既成概念から解放することを目指すGARAGE Program2期生「KISABURO KIMONO Project」のキサブロー(着物アーティスト)をナビゲーターとし、GARAGE Programを終了した2プロジェクトに加え、少し前に卒業した2プロジェクトの計4プロジェクトが活動を報告しました。
本レポートではその発表内容をお伝えします。
和菓子に関わるきっかけをデザインし、和菓子文化が息づく未来を探究する
登壇者:清水透和
プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/wokashication

「Wokashication」は、100年後も日常生活の中に和菓子があることが当たり前の世界をつくるため、デザインの視点から和菓子の提案を通じ、和菓子を食べる、楽しむきっかけをつくるプロジェクトです。
清水:100BANCHでは、和菓子×体験をテーマに「つくる体験・飾る体験・知る体験」と、体験をかけ合わせて様々なものをつくってきました。和菓子の種類としては、和三盆、琥珀糖、練り切りです。
和三盆は、サトウキビからとれた砂糖を型に入れて固めた和菓子で、これを箸置きとかけ合わせた「和三置き」を制作しました。季節感を感じる箸置きとして使えて、最後には食べられる和菓子で、デザインやプロダクトのコンテストでも賞をいただきました。また、和三盆は誰でも簡単につくることができると分かったので、地域でつくられる様々な原材料と混ぜ合わせて商品をつくったり、誰でも和三盆を簡単につくることができるフローの開発やワークショップを行ったりしています。
次は、琥珀糖を飾る体験です。琥珀糖は、外側がシャリッと、中がぷるっとした食感が魅力の和菓子です。砂糖と水と寒天でつくることができ、はじめはゼリーのような柔らかさですが、干すことによって外側がだんだん固くなっていきます。この琥珀糖を干す行為を、モビールとして飾るという体験に落とし込みました。干してでき上がる体験だけでなく、だんだん食べ頃になっていくのを楽しめるものになっています。
最後は、練り切りを知る体験です。練り切りは、季節の風物や情景を表現する“食べる芸術”とも言われている和菓子ですが、何を表しているのかわからない方も多いと思います。そこで“知ることでより楽しめるのでは”という仮説を立て、練り切りを最大限に楽しむためのパッケージデザインを制作することにしました。イラストと説明文でその造形について知り、より楽しく食べられるパッケージを現在制作中です。

清水:「3ヶ月のプロジェクトで“和菓子×体験によって新しい価値を生み出すことができたのではないか?”というところまでたどり着きました。ご清聴ありがとうございました。」と清水は話しました。
移動式ミニマム劇場〜見るものを限定しない公演を〜
登壇者:ソーズビーキャメロン
プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/tinytheater

「TinyTheater」は、移動式のノマド劇場で、人が集まる場所に劇場を持っていくことで、豊かな表現と豊かな批評による新たな劇場文化の創造を目指すプロジェクトです。
ソーズビー:武蔵野美術大学にいたときにクラシックバレエを広める活動をしたいと思っていたのですが、大学に踊る場所がなく、“じゃあ美大なんだし、箱をつくろうよ”というところからこのプロジェクトをはじめました。その後、100BANCHに駆け込み寺のように入り込んで、今回GARAGE Programを3ヶ月延長しました。前半の3ヶ月で大きな山も超えたので、このまま終わってもいいんじゃないかと思っていたところ、ベルリンに来ないかという話をいただきました。せっかく行くからには、きちんと仕事として依頼を受けられる状態にしたい。納得のいくクオリティにしたい。コラボレーションをもっとするにはどうやればいいのだろう。そんなことを考えて、料金表を作成したり、営業活動をしてスポンサーを募ったり、我々がやっていることを視覚的に分かってもらえるようにロゴをつくり直したりしてきました。営業活動の結果、スポンサーは見つかりませんでしたが、出演者もミニマムな形で、みんなでつくったものを現地に持っていき、なんとかベルリン公演を行うことができました。
100BANCHは、起業したり賞をとったりしている人たちがたくさんいる環境で、私たちも大学の有志学生の立場から社会人として仕事にしようという意識が芽生えたこと、また、人の新陳代謝も目まぐるしく起こったことも大きな変化でした。
「100BANCHでも変わらなかったのは、“もういい、疲れた、やめてやる”と思ったタイミングで、“ちょっとこういう話があるんですがどうですか?”と声がかかって、その一つをモノにすることで、また次のことにつながっていくという連鎖でした。TinyTheaterは終わりません。100年後も続きます。」とソーズビーは話しました。
新しい制服のカタチをつくり、学校教育をより良くする
登壇者:稲田駿平
プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/science-fiction-club

「Science Fiction Club」は、学生服を変えることを通して、学校教育を変えることを目指すプロジェクトです。
稲田:私たちの命題は日本の学生服を変えること、そしてそれをメディアとして学校教育全体を変えることです。制服は、没個性・全体主義・ジェンダー・価格高騰など、いろんな批判があり、制服自体をなくそうという動きも多いです。しかし、制服は、仲間意識を育んだり、貧富の差をなくしたりする装置として、有効な面もたくさんあります。よく学校の制服でみかけるチェック柄のスカートは、教師が見たときにスカートを裾上げしているのが一目で判断できるグリッド定規の役割なのですが一方、制服ディズニーなど、仲間意識を生み出す装置としても有効な部分もあります。
それで私たちが打ち出している方法論が「共通しているけれどバラバラな制服」をつくるというものです。制服は変数と定数の取り合いです。定数は校則、変数は個性です。相反するものを組み合わせて、多様なまとまりをつくります。
そうして、まずは制服のコンセプトモデルをつくりました。すべて生成りのキャンバス生地を用いて、ホリスティックにデザインすることで、全体に統一感を持たせています。一人ひとりが着ているものは違いますが、全体で見ると1つの集団に見えます。ただし、このモデルを実際の学校で使うのは厳しいので、これを元に実際の学校で使うことを想定した実施設計モデルを現在制作中です。共通したデザインシステムのもと、バラバラな制服をつくります。根幹となる2色を決め、グラデーションによってバラエティを生み出していきます。このカラースキームで制服をつくっていけば、その学区や校庭で遊んでる生徒をパッと見たとき、それぞれが違う制服を着ているのに全体として1つのまとまった団体になっているのです。そういったデザインスキームを学校ごとにつくることで、学校制服に多様な土壌をつくることができます。
例えば、1色しかない集団に少し違う色のものが入り込んでいたらすごく目立ちますが、元々が多様な土壌の集団に入り込んだら目立ちません。現在、スカートを履きたい男の子やパンツを履きたい女の子もたくさんいるのですが、実際に着ると目立ってしまいます。しかし、元々が多様な土壌であれば目立つことはありません。この提案はデザインの提案でありながらシステム自体の提案でもあります。
例えば、ユニクロのTシャツや古着屋さんで買ったパンツでも良いというルールにしたとして、さきほどのデザインスキームにさえ則っていればOKとすると、学校から制服を廃止する選択肢が生まれてきます。制服を廃止し、決まったデザインスキームの中で制服っぽい私服を着ることができます。そんな風に、グリッドのように揃って並んでいた定数が、変数によってバラバラになっていく学校教育を目指します。
「ナナナナ祭では私たちの制服を着ていただけます。現在、鋭意制作中で、1タームにつき12人ぐらいで着ていただいて渋谷のスクランブル交差点に繰り出そうと思います。みなさんぜひジョインしてください。」と稲田は話しました。
ユーザーがAIとリメイクデザインすることで実現するたのしいサーキュラーエコノミー
登壇者:加藤優
プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/hizumi
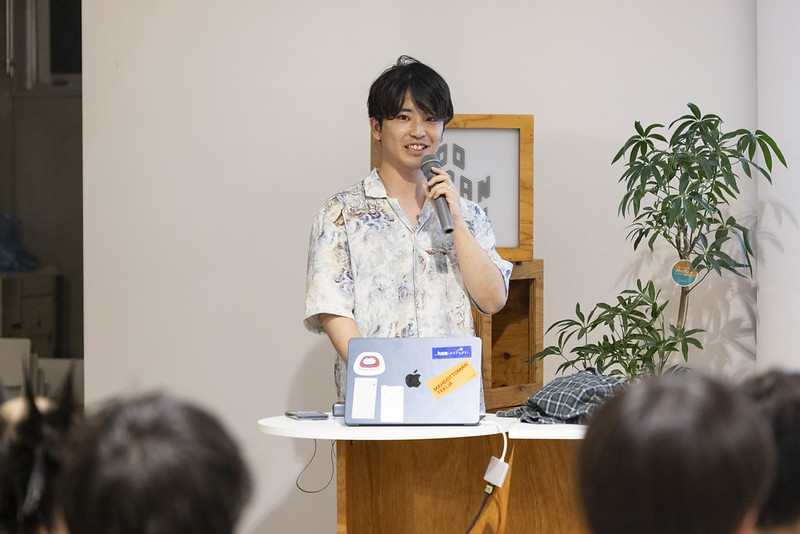
「HIZUMI」は、ユーザーが持っている服を使ってAIがリメイクデザインを生成し、そのリメイクされた服をユーザーが購入できるプラットフォームを開発するプロジェクトです。
加藤:100BANCHには2年前に入居して、今でも定期的に来て活動しています。AIを使って服のリメイクデザインをするプロジェクトをやっており、テクノロジーを活用することで、誰もが目の前の服の未来を考えられる世界を実現したいと思っています。
まずプロジェクトをはじめたきっかけをお話したいと思います。祖父が背広が大好きで家にたくさんあったのですが、その祖父が亡くなって大量の背広が廃棄されてしまうことになりました。そのとき、洋裁学校に通っていた祖母がそれをリメイクしてくれたのですが、ぼく自身でデザインの要望などを出すことができなかったことが気になっていて、もっとデザインを気軽にできたらいいなと考えました。ちょうど同じようなタイミングで、ファッション業界での大量の廃棄の問題などがあったこともあり、自分のエンジニア技術を使えないかと考えたのが、AIを用いて誰でもリメイクデザインができるプラットフォームです。データ化された服と自分が持っている服を組み合わせたリメイクデザインをAIが提案してくれて、それを実際に購入することができるプラットフォームをつくろうとしていました。
100BANCHへの入居以前から活動はしていましたが、100BANCHのタイミングでは、まず服づくりをしたいと思って、ファッションブランドの立ち上げを行いました。現在の社名にもなっているんですが、「.hzm」(ドットヒズミ)というブランドで、AIが起こすエラーをデザインに落とし込むというコンセプトのブランドです。100BANCHでは、実際につくった服を展示したり、その場でリメイクデザインの制作ができたりする展示を行いました。
その他にも、生地の破片を組み合わせて、3Dシミュレーションして、色々なデザインの可能性を探すようなシステムや、ピクセルから和裁の法被のデザインをつくるシステムなど、デジタルを使った様々な手法で服作り、リメイクを模索していました。
一方、これをもっと広いムーブメントにしたいと考えたときになかなかスケールしない事実に直面し、服づくりのプロセスを改善しようと活動方針を変えました。現在は、リメイクよりもっと前提の服の型紙を生成するAIを開発しています。服の型紙をつくるプロのパタンナーと呼ばれる職業があるのですが、AIで言葉から型紙を生成し、それを3Dにしてデザインを確認できるシステムをプロのパタンナー監修の元、開発しています。
「7月のナナナナ祭では『遥かなる他者へアップサイクル』というテーマで、その場でアップサイクルデザインをできる展示を行います。他にも、刺繍をつくるAIも開発中で、色々と実験をしている最中です。」と加藤は話しました。
実験報告会の各発表内容はYouTubeでもご覧いただけます。
Wokashication https://youtu.be/jLpAQpnl5yE?feature=shared
TinyTheater https://youtu.be/W0iyhCR9gNw?feature=shared
Science Fiction Club https://youtu.be/n1mFCo2Xusk?feature=shared
次回の実験報告会は7月24日(木)に開催。ぜひご参加ください!

(撮影:荒井孝治)

【こんな方にオススメ】
・100BANCHに興味がある
・GARAGE Programに応募したい
・直接プロジェクトメンバーと話してみたい
・官民連携や民主主義に興味がある
・ソーシャルイノベーションに興味がある
【概要】
日程:7/24(木)
時間:19:00 – 21:30 (開場18:45)
会場:100BANCH 3F
参加費:無料(1ドリンク付き)
参加方法:Peatixでチケットをお申し込みの上、当日100BANCHへお越しください
詳細はこちらをご覧ください:https://100banch.com/events/70020/