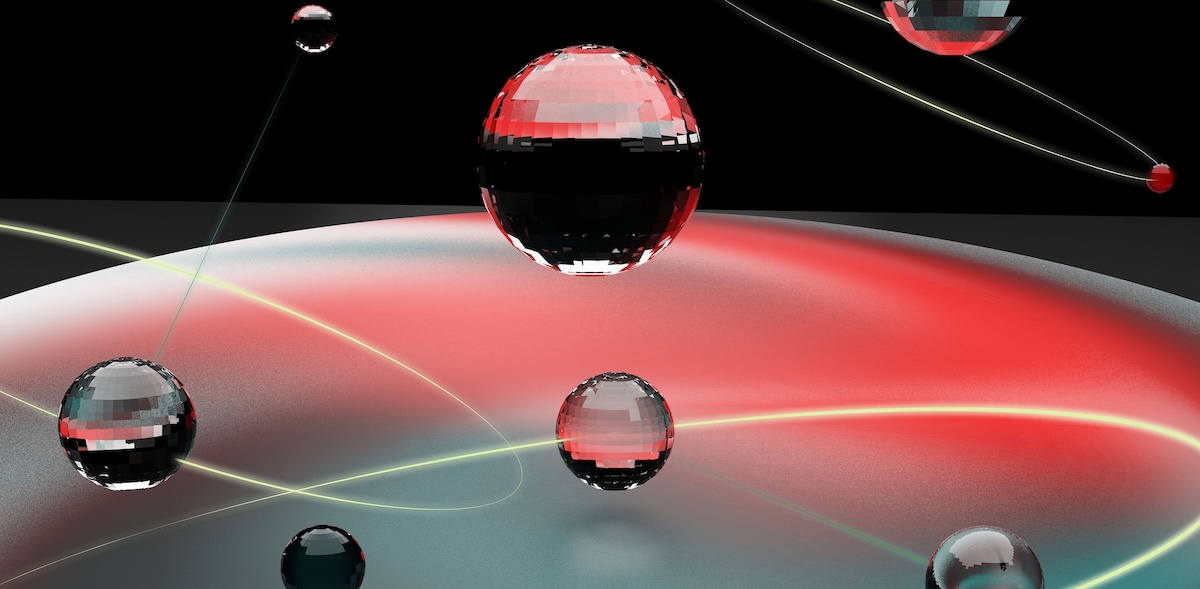
[DESIGNART 2024] オープニングイベント「生物×アート / 自然×デザイン」

日本最大級のデザイン&アートフェスティバル「DESIGNART TOKYO」に今年も出展した100BANCH。 GARAGE Program に集うプロジェクトの中から、今年は「生物×アート/自然×デザイン」をテーマに若手クリエイターの作品を展示するとともに、関連イベントも開催しました。
開催初日である10月18日(金)の夜にはオープニングイベントとして、今回の展示のテーマである「生物×アート/自然×デザイン」について、トークイベントを実施。パナソニック ホールディングス株式会社で万博推進担当の小川理子さんをゲストに迎え、株式会社積彩の大日方伸(GARAGE Program40期生)、株式会社BIOTAの伊藤光平(GARAGE Program8期生)という来年行われる大阪・関西万博に関係するメンバーで「自然と人間との共棲関係が深化する」をテーマにクロストークを行いました。本レポートではそのトークの一部をお届けします。
|
登壇者 大日方 伸 | Color Fab プロジェクトリーダー/株式会社積彩 代表 /GARAGE Program40 期生 伊藤 光平 | GoSWAB プロジェクトリーダー/株式会社BIOTA 代表取締役 /GARAGE Program8 期生 則武 里恵|100BANCHオーガナイザー/パナソニックホールディングス株式会社 技術部門 事業開発室 |

「生物×アート / 自然×デザイン」のテーマに変身した 100BANCH 3F にて実施
今回登壇する3 名は、来年の大阪・関西万博のパナソニックグループパビリオンの制作に向け、コラボレーションを推進してきたメンバーです。それぞれの活動や想いに触れながら、自己紹介からトークがはじまりました。モデレーターは、100BANCH のオーガナイザーであり、今回の共創をコーディネートしてきた則武が務めます。
小川:大阪・関西万博、正式名称は日本国際博覧会といって、日本の国家行事です。夢洲(ゆめしま)という大阪湾の小さな埋め立てられた島で開催されるのですが、大阪だけではなく近隣の京都や兵庫、奈良を含む関西広域連合など、様々な方と共同で進めており「いのち輝く未来社会のデザイン」がテーマです。パナソニックでは、私は元々エンジニアでオーディオ、ネットワーク事業、ブランド部門など、いろんなことをやってきて、現在は万博の担当です。今日はみなさんとお話できるのを非常に楽しみにしてきました。
則武:小川さんは、ピアニストでもいらっしゃいまして、かねてより多才で素敵だなと思っていました。今日はご一緒できてうれしいです。
大日方:株式会社積彩 代表の大日方です。ぼくの会社では3D プリントという技術で色々なものをデザインしたり、自分たちでつくったりしています。また、積彩という名前の通り、カラーリングをデジタルテクノロジーで解釈して、色彩豊かな花瓶や時計など新しいデザイン、ものづくりを行っています。今回の万博ではパナソニックさんの開発する「kinari」という植物繊維を原料とした素材を使って、3D プリントで葉っぱのようなオブジェをつくっています。そのほか「kinari」チームとはテーブルセットなど色んなものをつくっていて、素材の可能性を一緒に探求しています。
伊藤:株式会社BIOTA の伊藤です。ぼくたちは都市環境の微生物や生物多様性を定量的に評価し、そこから建築やランドスケープ、都市で微生物とどう共棲していくか、といったまちづくりのデザインをやっています。大学の学部生のときに100BANCH に採択いただいていろんな活動をサポートいただき、今は少しずつビジネスにつながるような活動ができるようになってきました。
則武:100BANCH は、DESIGNART2024 のテーマを「生物×アート/自然×デザイン」としていますが、積彩チームはテーマど真ん中のものを制作しましたね。
大日方:今回は素材からのスタートで、kinari という「ほぼ木」のような素材をどう調理するのか?がテーマでした。結構長い間、研究開発をしていました。
則武:パナソニックの「kinari」という素材は、セルロースファイバーという植物由来のサステナブルな素材です。今までカップなどの小さいもので使われていたのですが、もっと大きいもので使うことができないか、もっとサステナブルな使い方ができるんじゃないか、とコラボがはじまったんですよね。
大日方:3D プリントはサステナブルという言葉とセットで語られることが多いんです。3Dプリントは、削ったりせずに、必要なものを必要な分だけ吐出して造形していくものづくりなので、ほぼゴミが出ず、電力もそんなに使わないんですよ。でも、サステナブルという言葉はテーマ性のように語られることが多く、それを突破していくためには、サステナブルと言わなくても、人がそれを魅力的だと感じる状態にしていかないといけません。
それで今回はサステナブルからではなく、「素材本来が持つ自然性」から考えました。普段、デジタルデザインをするときは、いろんな線の集合体や複雑なパターンをつくりますが、人工的につくり出そうとすると、えぐみみたいなものが出て、ずっと向き合っていられないことが多いです。しかし、木の板や木目を見たときに、なぜこれはこんなに複雑なパターンなのにずっと一緒にいられるような気がするんだろう、みたいな不思議さを感じて、DNAに刻まれた何かがあるんじゃないかという気がしました。それで、ストレートに木からできた素材を木目のような家具に昇華できないか、と考えて、年輪のパターンみたいなものをつくって家具に転写してみました。
則武:「kinari」の持っている魅力を、どうデザインに活かせるかに挑んで頑張ってつくってくれたので、パナソニックの技術者がそれを見て「こんな風にしてもらえるんだ!」とすごく喜んでいました。素材のチームの中だけでは考えられなかった進化が、両者のコラボで実現できたのはすごくよかったなと思いました。
大日方:家はヒノキがいいな、みたいに、素材によって愛着のようなものがあるじゃないですか。手触りとか匂い、質感みたいなものが、人との生活に関わっていくと思うので、「kinari」らしさみたいなものも存在するんじゃないかと思い始めて、そういうところも出せたらいいなと色々と実験中です。

会場内に展示した、積彩×kinari の「年輪の家具」(写真左下)と「リーフオブジェ」(写真左上)。
則武:今回の万博では色々な素材にトライされていると思うのですが、小川さんはパナソニックのパビリオンをどのように考えていらっしゃいますか?
小川:私たちのパビリオンの名前は「ノモの国」といいます。松下幸之助が1932 年に250 年計画というのを発表しているのですが、「250 年かけて物と心が共に豊かな理想の社会を実現する」というものです。25 年を1 節として、それを10 節繰り返し、次の世代、その次の世代と引き継いでいって、どんどん良くしていく。自分を犠牲にすることなく、自分たちも人生を幸せに全うし、次の世代にも社会をよりよくしていってもらう、という哲学があります。
今回の万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」で、私たちの事業哲学、経営理念ととても親和性があると思います。モノはある程度豊かになりましたが、モノは心の持ちようによって色々と捉え方が変わってくる、いわば、心の写し鏡である。ということで、モノをひっくり返してノモ、それをパビリオンの名前にしました。このパビリオンで子どもたちがいろんな探索、冒険をしていく中で、自分の力を信じて一歩踏み出すきっかけになればいいな、という想いでつくっています。
コンセプトは「解き放て。こころとからだとじぶんとせかい。」で、世界規模の大きな社会課題を世界中の人たちが知恵を持ち寄りアイデアを出し合って、解決に向けてコラボしていこう、というのが今回の万博の役割、定義です。人間も自然の一部、モノも心も一緒で、土から微生物から植物、生物、もっと言うと月や太陽も、宇宙も全部つながっていて、そうしたらみんなでなにかできるんじゃないか、そういうイメージで「解き放っていこう」と。
大日方:「ノモの国」のコンセプト、めっちゃ好きです。ぼくはこの「解き放て。」を「未知化」と呼んでいます。学校の勉強は「既知化」で、教科書などで物事を理解し、知っている状態にしていくことですね。最初の25 年はそういう「既知化」が大事だったと思うんですが、そこからの25 年は「未知化」をやっていくことがすごく重要な気がします。知ったような気になっていることもリフレーミングすると、こんなに知らないことがあったんだ、と新しい事柄に気づき、そこでまたフレームをつくっていく。デザイナーの仕事は、「これってこういう風に見たらこんな魅力があるんだよ」と新しい気づきを与えていくことだと思っています。そういう高度なことを義務教育真っ只中の子どもたちと共有するのはすごくワクワクしますね。

則武:私はバックグラウンドがPR なのですが、世の中、何でもわかりやすく説明することが是とされすぎているなと思っていて。100BANCH の立ち上げは私なりの「未知化」のプロジェクトだったと思います。たくさんのプロジェクトがあって、とてもわかったなんて言えないのですが、わからないものをわからないまま扱いながら、その先を見たいな、というのが私の原動力になっているし、それをつくるのがデザイナーさんの仕事だというのは、なるほど! と思いますね。
伊藤:わからないものをわからないまま共に過ごす、まさしく「共棲」なのかなと思います。則武さんも100BANCH で、このプロジェクトはどういう意義があって、なんでやっているのか、を全部理解できるわけではないと思いますが、一旦受け入れるじゃないですか。わからないながらも受け入れるのは「共棲」なんだなと思いました。
大日方:微生物なんて本当に未知の塊ですよね。伊藤くんは微生物に対する姿勢で、あまり正解のようなことを言わないじゃないですか。その辺の話を聞かせてほしいです。
伊藤:微生物は毎年どんどん新しいものが生まれてきていて、図鑑をつくったとしても地球上にいる微生物の数パーセント程度しか載っていない状況だと思います。重要なのは、それをぼくたちが認知していないだけで、そこに存在してることは間違いないということです。よく、「除菌や滅菌で微生物をゼロにしよう」といったこともありますが、わからないからこそ、どう共にあるべきかを考えたくて、BIOTA ではそういったまちづくりにチャレンジしています。
万博では「ノモの国」の「大地」のエリアで、大きなセンサリードームをつくっています。内装は「菌糸」を培養したパネルを張り巡らせ、微生物と共棲するような空間、自然を体感できるようなドームをつくっているところです。今日後ろに展示している、菌糸のだるま、うつわ、下駄も同じ手法で、これらの素材はすべて土に還ります。最終的に、このパネルが土の中に埋められ、土中の菌糸のネットワークを多様化させたり、他の生き物の栄養になったりするといいなと思っています。

会場内に展示していた「KinSci」。キノコの菌糸でできています。
大日方:今回、「いのち輝く」「人間と自然」といったことを言っている中で、ぼくたちは圧倒的にモノにアプローチしながら、そのモノが何からできて、どう使われて、どういう風に使い終わっていくのかまでを考えているのがポイントかなと思っています。ぼくらのつくっているのもセルロース素材でリサイクルしやすく、別のモノに生まれ変わらせることが容易です。現代社会はモノを殺し続けているような社会で、例えば、ポップアップで人間が使い終わったモノは、素材としての寿命はまだあるのに殺されていくんです。そういう意味で人とモノが共棲できていないと思います。でも、面白いのが今、いろいろつくっている中で、「素材が足りない、間に合わない」という状況になっていて。
則武:「kinari」が人気でいろんなとこから引き合いがあるらしく、今回の万博では量が足りないかも?となったんですよね。
大日方:それなら、これまでつくったものや失敗物を素材に戻して使えばいいじゃないか、みたいな話になっていたりして。
則武:「kinari」はリサイクル性がすごく高いし、完全循環を目指したいですよね。今回は生分解性クラスのものを使っているので、土に埋めても自然に悪影響を与えず戻っていくというのも、循環の流れをつくるものです。展示会などでは数日のためにたくさんつくって、あっという間に壊してしまうみたいなことがありますが、今回の万博はいろんなところで「もう1 度使える」とか、「その後こういう風にしていこう」といったことが最初から語られていて安心しました。
則武:今回のテーマである「自然との共棲」ですが、どんなときに「自然」を感じたり意識したりしますか?
大日方:例えば「食事」の場合、調理して、食べて、ゴミとして排出して、といった流れの中に自分もいる感覚が持てるんですが、ものづくりの場合、モノがつくられる部分が遠くにあって、自分がその循環の中にいるイメージが湧かないんじゃないかと思います。資本主義、産業革命を経て、工場がどんどん都市から離れていき、知らないところでたくさんつくられたものが自分の手に届く。つくられる背景がわからないから使い終わった後にどういう循環に戻っていくかわからず、自分も循環の一部だという自覚が持ちづらい気がしますね。モノの一生、みたいな話でも、つくることをもう少し想像しやすくしたり、自分たちの身の回りに戻していくような活動が必要なんじゃないかなと思います。ぼく自身は、3D プリントでモノをたくさんつくっているので、その循環の中にいるイメージがすごくあります。
則武:つくるというプロセスが、人々の生活から遠くなってしまっているんだろうなと思いました。私は100BANCH のサテライトフィールドで徳島県の神山町にときどき行きます。そこに田んぼの仕事を教えてくれた84 歳のおじいさんがいるのですが、道具は全部自分でつくっておられたんですよ。道具が壊れたとき、私は「買いに行かなきゃ、修理に出さなきゃ」と思ったのですが、次に会ったときに「つくっておいたよ」と言われてびっくりしました。でも、つくれる喜びってすごいな、豊かだなと思って。
大日方:そういう人をファブ爺って言うんです(笑)。自分でつくるからこそ、どう修理したらいいかもわかるんですよね。壊れたときに、「捨てよう」じゃなくて、「修理しよう」と思えるのがすごく強くて豊かだなと思います。毎年、ミラノサローネという大きなデザインの展示会があって、ここ数年のテーマは「サステナブル」だったのですが、次のテーマは「クラフト」なんです。「サステナブル」で、モノがどう捨てられていくか、 どう利活用されていくか、にスポットが当たっていたのですが、「クラフト」でどうつくられるか、にあらためて注目することで、ちゃんとつながっていくことが示されたと楽しみにしています。

小川:私は、技術とデザインを担当していたときにミラノサローネに2 年連続で出展しました。日本の伝統工芸とエレクトロニクスを融合させたらどういうものができるだろうと、木工、金属、織物、日本の伝統工芸の人たちとコラボレーションしたのですが、日本の伝統工芸は、美しくて、でも日常生活の中で使う、という実用の美なんです。松下幸之助も、「伝統工芸が日本のものづくりの原点である」と言っていたのですが、そういう考え方がずっとつながっているんですね。
伊藤:ぼく自身はずっと微生物を研究しているので、体にいるたくさんの微生物が1 つの臓器のように機能している、共棲している他者、のような認識があります。サステナビリティの話とも関わってきますが、ぼくたちは自然を使って、モノをつくったり産業を生み出しているように、自然資本をうまく変換して地球上の都市に落とし込んでいますが、今は「戻す」ことができていません。アップサイクリングは、加工した自然資本を人間の経済圏の中だけで循環させていて、あくまでもステークホルダーは人間だけです。そうじゃなくて、一度使ったものを自然に還したり、分解して土中の生態系や植物に還してあげる。そういった単純なことで、今後、自然資本をどんどん活用していけると思うんです。バイオセンサリードームや「kinari」など、人が自然にもっと介入して、自分たちが使えるものを増やすために自然と共棲する、といった、ある種利己的な行いでも、もっといい社会がつくれるんじゃないかと思います。
小川:菌糸を使ったら他にはどんなことができるのでしょう。例えばウェアなどもつくれるのですか?
伊藤:海外でそのようなカンパニーがあって、菌糸のマッシュルームの上の部分を圧縮して服にしたり、ヴィーガンミートのようなベーコンにしたり、試験的に取り組まれてきています。代替品として便利というだけでなく、微生物とどう共にあるか、生活の中に彼らをどうやって忍ばせるか。ツールとしてどう使っていくか超えた先に、「どのように共棲していくか」というデザインがあるんじゃないかと思っています。
則武:私も以前、伊藤さんのワークショップに参加して菌糸のランプシェードをつくらせてもらったのですが、すごく不思議でした。菌糸とおがくずを混ぜて、どんどん白くなっていって、何で固まるんだろう?と。その働きに、「ランプシェードをつくってくれてありがとう」という気持ちになりました。
伊藤:「環境を整えてあげて人間が待つ」という行為ですね。生き物本位の行動なので人間ができることは少ないし、なかなか思い通りにいきません。ただ、そういったものと向き合いながら、不確実な中で生きていくことが、今の時代ではすごく自然ですし、最近はストレスなくできるようになってきました。不確定なことや、人間のようにコミュニケーションが取れないことも心地よく感じられるように頑張りたいです。
則武:面白い話ですね、最近はVUCA(ブーカ)の時代と言われるじゃないですか。昔は自然相手に不確定なことや未知なことも多かっただろうし、何でもわかると思いすぎているところが生きづらさになっているのかもしれないと思いました。
小川:私は新入社員のとき、研究所で毎日のように上長から「特許をかけ」と言われていました。「毎日毎日は、閃きませんよ」と言ったら「知っていることの中で考えているから書かれへん、閃けへんのや。知らないことだらけやと思え。」と言われたのを思い出しました。毎日、わかっていないことの繰り返しなんですよね。
伊藤:そうですね、やればやるだけ知らないことが出てきます。研究で論文を書いていて1個わかったと思ったら、ディスカッションでは10 個わからないことがでてきたりして。「死ぬまでできるのが、生物との向き合いだ」なんて思って、すごく楽しいですね。
大日方:ぼくらもそうです、わからないことをずっと愛しながらやっています。3D プリンターの世界でも毎日世界初のものが生まれてきます。ぼくらはデジタルデータとマテリアルの組み合わせでどんな視覚表現ができるかをよくやるのですが、「こんな変化になるんだ!」みたいなものが出てきたりするんですよ。
伊藤:ぼくが学部生のときに、大日方くんが色の変わるカラフルでキラキラしたボールをとても嬉しそうに持っていたことを今思い出しました。
大日方:そのボールをTwitter にあげたら、たくさんの反響をいただいて。そのときぼくは、自分の好きなものや、やりたいことがわかっていない状態でそれを投稿したんですが、投稿を見た人から「君はそういう色に興味があるんだね」など、自分でも思ってもいなかった解釈がたくさん出てきました。それで「自分の個性ってこういう感じなのか」と自分が定義されていって。
伊藤:できたものをぱっとSNS に出せる時代ではあるからこそ、ですね。自己が形成されていない状態でそれをするとフィードバックが辛いときもあるけれど、それによってものづくりが加速することもあるから一長一短ではあります。
大日方:そうですね。ぼくはアイデンティティを、自分で定義するものじゃなくて、他者や、自然、循環、人のつながりとかの中で形成されていくものだと思うので、その中の一部であるっていう感覚がずっとあります。
小川:わかります、まだ見ぬ自分が何かの瞬間にヒュッと出てくるわけですね。私はジャズをやっていますが、ジャズはインプロビゼーションの塊、常に即興なんです。例えばピアノとギターの二人でプレイするとき、ギターの人がフラっとやって、それに対して私が即興で応えて。そうやっているうち「あれ、何これ?」って、今まで自分が思いもしなかったような音楽が生まれたりするんです。他者によって気づかされること、結構あるんですよ。
大日方:そうですね。だから「ノモの国」は、子どもたちとのセッション、になればいいですよね。
小川:子どもたちとのセッション、素敵ですね。いただきます(笑)。
大日方:ぼくはつくるもの、デザインするものはすべてセッションだと思っていて、見る角度によって色や表情が変わったりするようなインタラクティブなものをいつもつくっています。だから、完成しきらないものをどう届けるかを常に考えていて。今回の「ノモの国」のコンセプトも子どもたちとセッションする何かがつくれればと思いますし、他者や自然とのつながりの中で何が生まれてくるか、今後も模索していきたいと思います。
伊藤:今日はいろんな気づきがありました。万博についても大日方くんのプロジェクトやパナソニックのパビリオンがどういうものなのか、改めて知れてすごく良かったですし、DESIGNART の作品の話ができたのもとても良かったです。
小川:みなさん日々、自然や微生物などいろんな未知なものと一緒に成長、進化されていますよね。わたしもいくつになってもみなさんと一緒に進化していきたいです。今日は本当にいいセッションでした!
クロストーク終了後、会場ではドリンクを片手にDESIGNART 展示作品を鑑賞し、作家・登壇者との歓談を楽しむ来場者の方々の姿が見られました。
