
第4章:[偏愛×創造] わたしだけの熱狂が社会を揺らす

誰にも理解されなくても、それでもやりたい、伝えたい、続けたい。そんな「わたしだけの熱狂」が、やがて人を動かし、社会を揺らすエネルギーになる。
「ナナナナ祭2025」初日のカンファレンスデー第4章では「[偏愛×創造] わたしだけの熱狂が社会を揺らす」を開催。偏愛と創造のあいだを生きる登壇者たちが、内側からあふれ出す衝動の話を、偏りのままに語りました。
index
|
登壇者 野々村 哲弥|Omoracy リーダー/株式会社ロジリシティ 代表取締役 高倉 葉太|INNOQUA リーダー/株式会社イノカ CEO モデレーター |
── イベントに登壇するのは、100BANCHでプロジェクトを推進してきた2人。サンゴへの偏愛から世界初の人工産卵に挑み、いまや研究開発を手がける会社へと成長させたGARAGE Program12期の高倉と、バンジージャンプのスリルをVRで再現し、日本から世界へ新しい体験を届けているGARAGE Program15期の野々村です。それぞれの偏愛が、人や技術を巻き込み、社会を揺さぶるプロジェクトへと広がっていっています。
高倉:株式会社イノカの代表の高倉と申します。私はサンゴが大好きです。この会社もサンゴ好きの2人が出会ってはじまりました。弊社のチーフアクアリウムオフィサー、つまりおそらく世界で唯一のアクアリウム担当役員である増田は、自宅に1トンもの巨大な水槽を35年ローンで導入してしまうほどの偏愛の持ち主です。はじめて出会ったとき、彼は工場で見回りの仕事をしていて、サンゴの知識はまったく活かされていませんでした。「これはもったいない」と思ったことから、この会社を立ち上げました。最初にはじめたのは教育活動です。当時はサンゴの水槽をつくることくらいしかできなかったので、100BANCHの2階にサンゴの水槽を置かせてもらい、サンゴをみんなに知ってもらう活動をはじめました。おかげさまで、日本全国の様々な場所、施設に水槽を持っていって、子どもたちに生きた本物のサンゴを見せる教育プログラムを展開することができました。
また、子どもたちだけでなく大人にも生き物好きはたくさんいるはずだ、ということで「INNOVATE AQUARIUM FESTIVAL」を100BANCHで開催させていただいて、生き物好きの人たちを発掘する活動も開始しました。その結果、自宅でマングローブ林をつくっている人や、サメのために生きている人、生き物好きの大学教授やビジネスマンなど、どんどん生き物好きが集まってきました。みんな生き物が好きという共通点はありつつも、バックグラウンドが多様なメンバーが集まった会社になってきました。いろんな社員が集まったおかげで、これまでできなかった世界初のサンゴの人工産卵にも成功することができました。また、扱える領域も広がり、企業の皆さんと新規事業をつくったり、研究開発を行うようになってきました。サンゴの教育活動に使っていた水槽は、今はデータをとるための水槽に変わっています。私たちはこれを「環境移送技術」と呼んでいて、実際の海で試す前に水槽で実験を行うことができます。具体例としては、サンゴに優しい日焼け止めをつくる研究や、鉄をつくる際に出る鉄鋼スラグを海に廃棄するとどうなるかの研究などがあります。当初はただの生き物好きの変態の集まりでしたが、今ではコンサルティングや研究委託を受ける、そんな会社に成長しています。
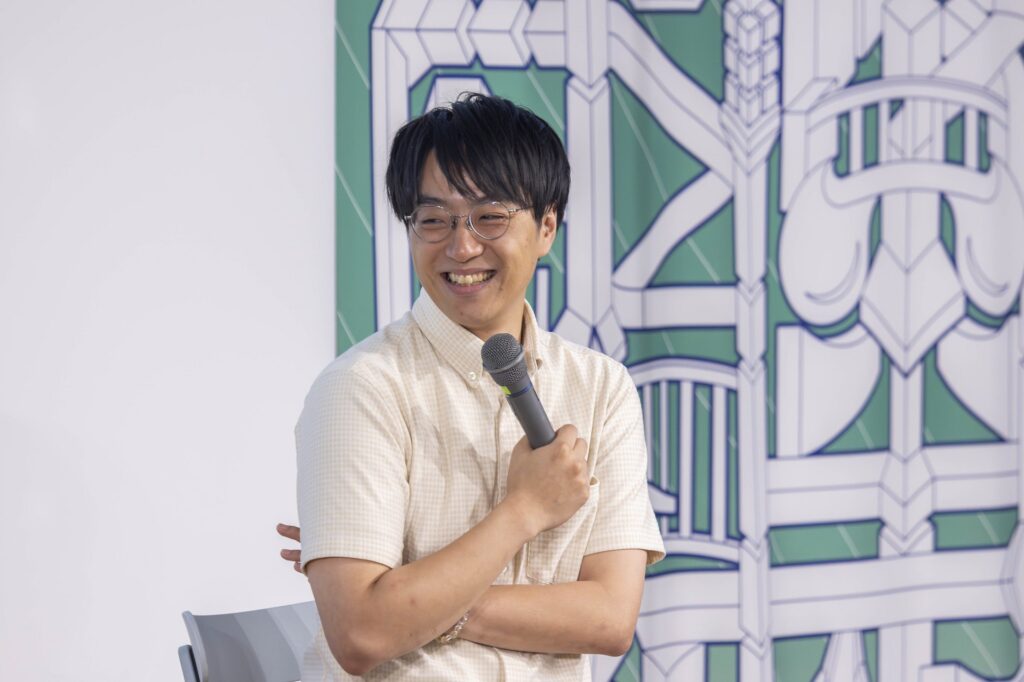
野々村:面白い新しいドキドキ体験をつくるOmoracyというプロジェクトで2018年に100BANCHに入居しました。私はバンジージャンプが大好きなんです。バンジージャンプは場所ごとに個性があり、いろんな飛び方があるのも楽しいのですが、僕が何より好きなのは、飛び込む前の「目の前の現実と思えない怖さ」に向き合って飛び込む瞬間です。心を揺さぶられ、人生を揺さぶられるような体験になるところが魅力だと思っています。その体験をVRで体感してもらえるようにサービスをつくろうと、100BANCHに入っていろんな体験装置をつくってきました。
元々は会社員でしたが、会社を辞め「バンジージャンプで食っていくぞ」とプロトタイピングを色々とつくって、これはいけると思って会社化しました。そして、より安全性が高い体験、飛び込める仕組みをつくってイベント業をはじめましたが、コロナ禍が来てしまったんですね。それでも、いろんな場所でイベントを重ねていくことができました。今では東京タワー、大阪のあべのハルカスの展望台で毎週末、レギュラー開催しています。最初は手動だった装置も現在は、遊園地の機械のように自動で動く装置になっています。こういった取り組みが評価されて、クールジャパンDXアワードで特別賞をいただいたり、先日も、AWE USAという大きな展示会でベスト賞をいただくことができました。日本から世界に向け、バンジージャンプの魅力を伝えていくサービスを広げていこうとしているところです。

── サンゴにバンジージャンプと、一見ニッチに見える偏愛が、仲間を巻き込み、プロジェクトを立ち上げ、社会を揺さぶる挑戦へと変わっていきました。「好き」を原動力に走り続けてきた軌跡やその裏側を聞いていきます。
則武:高倉さんは小さいときからサンゴが好きだったんですか?
高倉:サンゴと出会ったのは高校2年生のときです。生き物はその前からずっと好きでした。
野々村:僕がバンジージャンプで初めて飛んだのは大学4年のときです。スカイダイビングよりもスキューバダイビングよりも、もっと心を揺さぶられる。こんなすごい体験はなかなかないぞ、と思って、バンジージャンプの伝道師みたいになっていきました。
則武:すっごく楽しかったということと、伝道師にまでなるのって、結構差があるように感じますが、どうなんでしょう?
野々村:今って「推しエコノミー」があるじゃないですか。自分の好きなアイドルを推すとき、自分だけが思う「ここがめっちゃいいよ」って、人に語りたくなると思うんですよ。僕はそういうノリで「バンジージャンプ、あそこ立ったらこんなにヤバいんだぜ、俺の推しを聞いてくれ!」みたいな気持ちがすごく強かったです。
則武:なるほど。100BANCHではそれを「発症した人」って呼んでいるのですが、そういう人がひとりいると周囲に「感染」していくんですよね。私自身、高いところは得意じゃなかったけれど、野々村さんの「感染力」があまりにも強すぎて、気づけばバンジージャンプの魅力やVRバンジーの説明をできちゃうようになっていました(笑)。
高倉さんも「発症」した人なので、サンゴの魅力とか、水槽の魚について、イノカのプロジェクトメンバー以外の人にも教えたりしていましたもんね。熱い人の周りには「感染させられちゃった人」がたくさん出てきますね。高倉さんがサンゴにハマった最初のきっかけは何だったんですか?
高倉:家にアクアリウムが置いてあったんですが、飼育放棄されてたんです。それで代わりに面倒をみはじめたのがきっかけです。最初はグッピーやネオンテトラからはじまったのですが、次第に40〜50代のおじさんたちと一緒にアクアリウムショップを回ったり、どんどん沼にハマっていきました。

則武:すごくたくさんの種類がいるわけですもんね。そこからだんだんと世界を広げていって。小さいときから、ずっとサンゴを好きであり続けたんですか?
高倉:大学のときはいったん中断していた時期があります。世の中のあるあるですけれど、生き物好きってどこか社会から憚られている空気があると思うんです。人に「生き物が好き」ってあんまり言えないし、言っても評価されないんですよね。好きだったピークは小学生で、大学のときは、普通の大学生みたいにサークル活動に打ち込んで、サンゴにはあまり向き合っていなかったです。
則武:なるほど。自分が本当に好きだと思っていても、中高生の時期は言えなかったんですね。それはどうしてなのでしょう?
高倉:当時は「昨日のテレビ見た?」みたいな同調圧力が強かったですね。みんなが好きなものを好きじゃないといけない、みたいな空気がありました。
則武:そっちに合わせにいっていた、と。野々村さんはどうですか?
野々村:僕がバンジーにハマったのは大学の頃で、みんながいろんな趣味を持っているのは普通のことではあったのですが、やっぱり同調圧力みたいなものはありますよね。だからこそ、本当に自分が好きなものを言えるような人間になりたいな、というのは、物心ついたときから感じていました。
則武:今の2人を見ていると、好きと言うのをためらっていたなんて想像もできませんね。野々村さんがあれだけのスピードでプロトタイプをつくってアップデートしてというのを回し続けていたのは尋常じゃないと思っていたんですが、そこまでできたのはどうしてだと思いますか?
野々村:当時は3ヶ月、半年がすごく濃密で、あのとき2週間ぐらいでやろうとしたことを今やろうとしたら、おそらく半年はかかると思います。それくらい濃度が違いました。いくつか理由はあるんですが、大きな一つは退路を断ったことです。会社員を辞めて、「バンジージャンプで食っていく」と。毎日、「昨日よりも何かプラスアルファになること」を考えて、実際にやってみて、手応えを確かめて、というのを自分に言い聞かせながらやってました。正直、会社を辞めて急にバンジージャンプをつくり出すなんて「気持ち悪いやつ」だと思います。でも人からどう見られるかは気にせずやっていましたね。
則武:2週間でやった実験が半年かかるという話がありましたが、やっぱり2週間の密度の濃さがあったのですね。アップデートのスピードも本当に早かったので、めちゃくちゃ実験したんだろうなって思います。
高倉さんは一時期サンゴから離れていて、もう1回サンゴに戻って会社までつくってたくさんの偏愛の人たちとお仕事をされていますが、ここまでどうやってきたのかもう少し教えてもらえますか。
高倉:僕も「普通の世界」で生きている中で悶々とすることはあったんですよね。大学の研究室でAIの研究テーマを考えていても、「自分にしかできないことなんてあるのかな」と感じていて。そんなとき、100BANCHのように変態たちが自分の人生を振り切って自由に楽しそうに生きている姿を見て憧れて。自分はサンゴが好きだったし、サンゴと自分がやったAIを掛け合わせるなんて他に誰もやっていないし、これはイノベーションじゃん、と思ってこの世界に来てしまいました。普通のコミュニティの中で沸々とフラストレーションを抱えている人はたくさんいると思うので、彼らにこんな楽しい世界もあるんだよと見せてあげれば、結構こちらに来てくれるんじゃないかなと思っています。
則武:やっぱり「楽しい」ということなんですね。
高倉:そうですね。自分が好きなことや学んできたことがそのまま活きてくるので。元々起業は考えていましたが、「変態たち」に出会ってなかったら、自分はおそらく、ありがちなAIを使ったマッチングサービスなどをつくって人生を終えていたかもしれません。

則武:「渇望」というか、自分の行きたい道や、「こうありたい」という姿を強く求めたのかな、と思いました。でも高倉さんが100BANCHに入居していた頃は、今やっているようなサービスが見えていたわけじゃなかったので、当時はいろんなことやっていましたよね。
高倉:あのときは、水槽がつくれるだけでしたね。
則武:水槽をつくってくれて、そこで育てた海ぶどうを食べさせてくれたり、ナナナナ祭で試食会もやりましたよね。いきなりパナソニックの社長に「会社に水槽を置いてください」ってメールを送って営業したこともありましたね。でも、それぐらいチャンスを掴もうとしていた、突破口を見つけようとしていた、というのはすごいなあと思っています。そういったチャレンジの原動力って、2人はどういうところにあると思いますか?
野々村:僕は高校生のとき、お笑い芸人になりたかったんです。普通の人が普通に考えていたら出てこないようなアイデアを生み出すのがすごく好きで、そのアイデアで生計を立てたいと思っていました。大学のサークルでイベントをやったときに生まれる熱狂みたいなのもすごく好きで、自分が良いと思ったものを自分のエッセンスで世の中に出したいという思いは強くありました。強いアイデアって、それ自身が増殖したり広がっていったりするという意味で、生き物だと思っているんですよ。僕がバンジージャンプにこだわったときに、「VRでバンジージャンプを体験できる」という一番良いアイデアが出たので、それによって今も続けられてるのかなと思います。原動力は、そんな感覚です。
高倉:僕は「なんで頑張れているか」と聞かれるといつも答えに困ります。自分が好きでやっているだけで、別に仕事だともあまり思っていないからです。さきほど野々村さんのお笑い芸人の話がありましたが、僕も目の前に見えている人をまず笑わせたいというか、目の前の人が楽しそうにしていたり、面白がっているのがすごく好きなんです。自分たちが見えている範囲に、めちゃくちゃ生き物が好きな人たちがいて、その人たちと話していると、自分も知的好奇心をめちゃくちゃにくすぐられます。
そういう意味では、多くのベンチャーのように「いつまでに上場だ!」といった目標を掲げなかったのは大きかったと思います。地に足がついて、自分が仲良くしている人たちといられる環境がある。今が自分にとって一番心地よい場所なので、頑張って当然、みたいな感覚なのかなと思います。
則武:でも、その「心地よい状態」を保つために、そういう場をつくり続けているんですよね。そこがすごく大事なポイントなんだろうなと思いました。
── 自分の「好き」「熱狂」について会場の皆さんとも一緒に考えてみました。自分の中で「偏愛」と言えるものは?なかなか思いつかない人は「7歳のときに好きだったものは?」というテーマで周囲の人と語り合ってみました。

則武:自分の偏愛や大事にしていることを発揮して、社会に影響を与えていく、社会を揺らすには、どのように取り組み続けるのが大事だと思いますか?
野々村:やっぱり、今は会社として活動しているので、関わってくれている人たちが不幸にならないようにすることはすごく意識しています。だけどそれと同時に、自分がリスペクトするバンジージャンプ、VR体験装置をもっともっとアップデートしたい、まだまだこんなもんじゃない、という気持ちもあります。一言ではなかなか言いづらいですが、自分の納得感も大切です。「これだけ頑張ったから関わってくれている人たちも喜んでくれるだろう」「これだけ頑張ったからバンジージャンプ装置もいけるだろう」と思える納得感を求めてやっているのかもしれません。僕は、深い自己承認欲求があるんです。自分が良いと思うものを、「本当に良い」と思ってほしい、と。自分のこだわりのポイントを、とにかく社会にわっと出して、それが素晴らしいと言われることをすごく求めていて、そこを目指して頑張っています。
則武:こだわったときの野々村さんって、本当に潜って考え尽くしているんですよね。すっごく考えて、こだわりのポイントを探しているし、そろそろ決めてもらわないと進められないタイミングでも、すごく何かを探してる!みたいなオーラを出していて、こだわりの強さを思い出しました。高倉さんはどうですか?
高倉:弊社は社員が全員、そういう偏愛を持っている人たちなので、社内教育としても合致するテーマで、僕もずっと考えていろんなことをしています。自分が好きなものを社会に広げていきたい、知ってもらいたい、というのはすごく大事な気持ちですが、それを実現するためには相手のことも知らなきゃいけない、というのを僕は会社の中で伝えています。イノカでは昔、偽物のサンゴを置いている病院に電話をして「本物のサンゴを置きましょうよ」って話をしていたんですが、全然売れませんでした。理由はシンプルで、なぜ相手がわざわざ偽物のサンゴを置いているのかを考えなかったからです。本物だとコストが高いとか、子どもたちの癒やしのために置いているので、偽物でも本物でもあまり関係ない、みたいな。振り返ってみると、そういうことを理解せずに自分の好きを相手に押し付けてしまっていました。自分の好きなことを世の中に広げていきたい人こそ、他人の好きも尊重できるようにならなきゃいけないと思います。
則武:自分が熱中しているもの、熱狂しているもの、自分のアイデンティティに近いものが、社会を揺らすようになると、生きていてもっともっと楽しくなると思います。自分の偏愛を表に出して言ってみて良かったですか?
高倉:そうですね、言わなきゃはじまらないと思います。相手がどういう表情をしていても、目をバキバキにして言い切るのが大事です。もう二度と会わないんじゃないか、というような人には、とにかくもう一か八かで伝えれば「やばい人だ」と思われるかもしれないし、逆に評価してもらえるかもしれない。昔から応援してくれている方がいるのですが、僕が相手の気持を考えずにピュアに話していた時期があったからこそだと思います。言ったほうが夢が叶う可能性がどんどん高まるので、絶対に言ったほうがいいと思います。
野々村:僕はバンジージャンプを50回しか飛んだことがありません。やっぱり上には上がいて、もっと飛んでいる人もいるだろうし、「バンジージャンプが好き」と言いづらい、というのは結構ありました。でも、バンジージャンプのどういうところが好きなのか、自分の中で言語化して、例えば「場所ごとに個性があるから好き」「飛び方にバリエーションがあって色々楽しめる」とか、そういう自分なりの言葉で伝えればいいと思います。自分の感情は自分のものなので、「俺は好きなんだから言わせろ!」ぐらいの気持ちで割り切るのが大事なんだろうなと思います。
則武:本当にそうですね。自分の気持ちを正直に出してみることからしかはじまらないし、それを「いいね」と思ってくれる方もたくさんいると思います。100BANCHには、そういうムードもあるし、そんな風にはじまっていることも多いです。今、自分の好きなことについてちょっと話しにくいなと思っている方も、どんどん出していただきたいですし、100BANCHもそういうムーブメントを起こせたらいいなと思っています。
